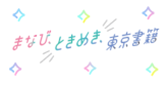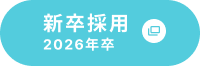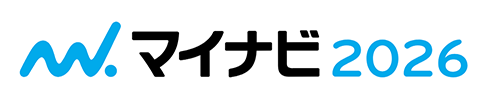仕事を知る
職種は大きく3種類。
各部署の連携を深めながら、時代の変化に即応し、
日々業務に励んでいます。
制作部門

東京書籍が発行する商品を制作する部門です。教科書・教材はもちろん、様々な商品・サービスを、紙からデジタルまで、様々な媒体での制作を行います。
小学校・中学校・高等学校のほぼ全教科の教科書を発行しているのが、東京書籍の特長です。
編集者には、それぞれの教科の専門的な知識だけでなく、原稿整理や校正などの編集技能、印刷に関する知識、学校現場や教育動向に対する理解力、会議進行の能力、デザイナー・カメラマンなど 外部関係者との折衝能力などさまざまな能力が求められます。しかし、より良い教科書をつくるために何よりも必要なものは、子供たちの未来を創る仕事に携わっているという責任感と熱意です。
また教科書事業だけでなく、学力調査などの評価関連事業や一般書・日本語検定の事業も展開しています。子供たちの学びと教育業界の発展に貢献するため、幅広いジャンルの商品・サービスの制作を担っています。
教科書ができるまで
【教科書・デジタル教科書】
・小・中・高等学校の教科書、教師用指導書、副読本の編集
・デジタル教科書の制作
教科書の編集者は、4年のスパンで教科書づくりに取り組みます。大学や現場の先生などからなる編集委員会を組織し、教育課程の方向性や学習指導要領を踏まえ、大枠の方針を決定するところからスタート。テーマごとに企画立案を進め、執筆・作画依頼、撮影、デザイン、入稿から文部科学省への検定申請・修正対応まで、編集業務全般を担います。あわせて、学びを広げ、深めるデジタルコンテンツの制作も行います。多くの著者や外部の制作会社等との連携が必要になるため、調整力やチームワークの意識が欠かせない仕事です。
-
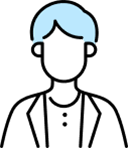
この国の知的成熟を支えているという大げさな責任感を持てるのは、教科書の編集者という仕事ならではだと思います。
すこし大げさに聞こえるかもしれませんが、教科書を編集するというのは、私たちが生きる共同体の「知的成熟」に責任を持つ、ということだと私は思っています。たとえば国語という教科では、学び手の言葉の力を養うことに最大の主眼が置かれています。というのも、私たちは言葉によって他者を理解し、そして社会を構築しているからで、つまり、言葉の力を身につけることによってはじめて、共同体を住みやすいものに維持することができるということです。数学も理科も社会も英語も、それぞれの教科の仕方でこの国の知的成熟を支えていますが、このようなちょっと大げさな責任感を持てるのは、教科書の編集者という仕事ならではだと思います。
-

教科書づくりに関わる全ての人の「子供への思い」を実現できる教科書をつくりたいと思っています。
教科書づくりに関わるすべての人の「子供への思い」を実現できる教科書をつくりたいと思っています。著者の先生方はもちろん、デザイナーは子供が見やすいレイアウトを考え、カメラマンやイラストレーターは学習内容が子供に伝わる写し方・見せ方を考えるなど、それぞれ「子供への思い」を持っています。ときには意見が食い違うこともありますが、編集者は、妥協せずに意見を交わし、とりまとめ、形にすることが仕事です。
-
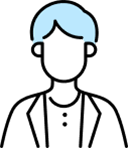
限られた時間の中で、いかに効率よく作業や議論を進められるか、自分の力が試されるのはこの部分だと思います。
この仕事を行うには、スケジュール管理が大切だと思っています。意見を交わし合うにも、とりまとめることにも、形にすることにも、やはり時間が必要です。ですが時間は限られています。その限られた時間の中で、いかに効率よく作業や議論を進められるかがカギになります。例えば編集会議であれば、議題の立て方や、焦点、重点の置き方などを事前に練ることで、効率よく有意義な会議が進められます。これからの自分の力が試されるのは、この部分だと思っています。
【デジタル教材・Webサービス】
・小・中・高等学校のデジタル教材の制作
・DX関連の教育ソリューションの開発
ICTの特性を生かしたデジタル教材の制作を行います。担当者は外部のシステム制作会社とも連携しながら、制作ディレクション全般を担います。既存の教科書に紐づく教材はもちろんのこと、近年では教育現場にとどまらず、家庭学習や塾などを対象とした教育ソリューションも展開しています。「デジタルツールを使ってどのようなサービスが提供できるか」を考えて実現していける、手応えとやりがいの大きな仕事です。全ての子供たちの可能性を引き出す教育の実現に資することを目標に進めています。
-
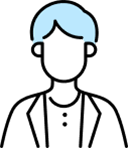
何かをゼロからつくりたい人には非常に面白い部署だと思います。
一般にソフトウェア制作の分野では分業が進んでいますが、東京書籍の場合、ソフトウェアの企画提案からシステムの構築、制作、運用・運営まで、細かい分担があるわけではありません。企画することが好きな人なら、入社後すぐに企画づくりに関われます。何かをゼロからつくりたい人には非常に面白い部署だと思います。
-

商品のシステム構築からディレクション作業まで。「使いやすくなったよ」の言葉がやりがいに繋がっています。
私は商品のシステム構築からさまざまなディレクション作業にかかわっていますが、制作に携わった商品を使っていただいている先生から「こんな機能があったらいいね」というヒントをいただき、その機能を追加できたときには、とてもやりがいを感じます。機能の追加は大変な作業ですが、「使いやすくなったよ」と、お礼の電話を先生からいただくと、この仕事を選んでよかったなと感じます。
-
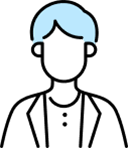
社内・社外問わず、本当にたくさんの職種の方に出会い、多くの刺激を受けながら企画を形にしていく、そんなところに魅力を感じます。
教材制作の過程では、本当にたくさんの職種の方に出会います。学校の先生方をはじめ、プログラマーやデザイナー、ディレクター、ナレーターなど、社内だけでなく社外の方ともアイデアを出し合い、多くの刺激を受けながら企画を形にしていける、そんなところに魅力を感じます。各分野のプロの方々なので知識も豊富ですし、それぞれのご意見の背景には深いお考えがあります。さまざまな人柄に触れ、自分自身も成長していけることが、仕事のやりがいにつながっています。
【評価関連】
評価関連事業の中核は「学力調査・学力診断テスト」の教育評価の分野です。全国の児童生徒の学力向上を測るため、学力調査などの商品開発に取り組んでいます。全国基準の学力調査を、調査問題から成績処理、考察資料までトータルに提供するとともに、各自治体独自の学力調査の受託開発も行なっています。また、小中学校用の生活学習意識調査、体力テスト、先生方の校務や評価を支援する校務支援システムなど、分野は多岐にわたっています。
教科書づくり100年以上のノウハウと最先端の評価・統計理論が融合してこそ、高い信頼が得られます。
-
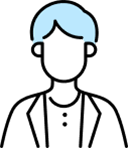
教育事業はイノベーションを起こしづらい分野と思われがちですが、実は新しい情報に敏感な人、教育の変革に意欲がある人に向いていると思います。
自治体ごとに教育課題があるので、それに対応した問題をつくる必要があり、自治体の先生や大学の先生と話し合うことが頻繁にあります。課題に応じた問題をつくるのは難しいですが、先生方のアドバイスをいただき、納得のいくものができたときはやりがいを感じます。
教育事業はイノベーションを起こしづらい分野だと思われがちですが、実は、新しい情報に敏感だったり、教育をよりよく変えていこうとする意見や意欲がある人に向いていると思います。他部署との連携を密にして真剣に議論し、そこから生まれるアイデアを形にできればいいなと思います。
【一般書】
教科書会社としての東京書籍ブランドの強み・総合力を活かし、教科書だけでなく一般書籍も出版しています。
著名な作家による文芸書、最新の話題や情報を盛り込んだ人文・自然科学書、食や旅をテーマにした美しいカラーの実用書、個性的な写真集、世界的に評価されている海外の大型図鑑、東京書籍の強みを活かした中学生向けの教科書準拠教材および高校入試用の教材など、さまざまな分野の書籍を多数出版しています。また、そのうちの多くは電子書籍としても展開し、なかには海外へ版権を輸出しているタイトルもあります。
販売時にはDXも活用しながら多様なプロモーション活動を行います。
-

編集者の私にできることは、読者がどんなものを望んでいるか、誠実に向き合い、真面目に考え続けることです。
出版社によって異なると思うのですが、東京書籍での一般書の編集者の仕事は、企画を立てることと、本という形にすることの2本柱です。編集者の私にできることは、これからこの本を手に取るであろう人が、どんなものを望んでいるのかということに、手を抜かないで誠実に向き合って、真面目に考え続けることです。著者にとっても、本はキャリアの一部になりますし、その方にとっては初めての本となることも多く、今後の名刺がわりになるかと思うと、中途半端なものは絶対につくれません。著者やそのジャンルのファンに対しても、誠実に向き合いたいと常に思っています。
【日本語検定】
東京書籍は日本語検定委員会が主催する日本語検定に協賛しています。検定事業部は、その日本語検定の問題を作成したり、関連問題集などを作成したり、更には販促物の企画・制作、メディア媒体を活用した広告企画などのプロモーション企画も行い、日本語検定を支援しています。
さまざまな企業や教育機関に検定をご案内し、『日本語検定』の普及を通じて、教育や文化の発展に貢献することを目指しています。
-
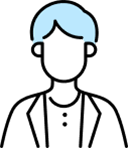
「今必要な日本語の力」に向き合っています。
検定問題を作成するチームの一員として働いています。検定では、いろいろな問題を出題していますが、特に総合問題を手掛けるときにやりがいを感じます。総合問題は、日本語検定の6領域の力を横断的に問う、文章や図表の読解問題ですが、「国語に関する世論調査」、大学入学試験、更には毎日のニュースや検定問題の作成にご協力いただいている先生がたのお声をヒントにして作成しています。今必要とされている日本語の力がどのようなものかを考え、問うことは、とてもクリエイティブでやりがいのある楽しい仕事です。