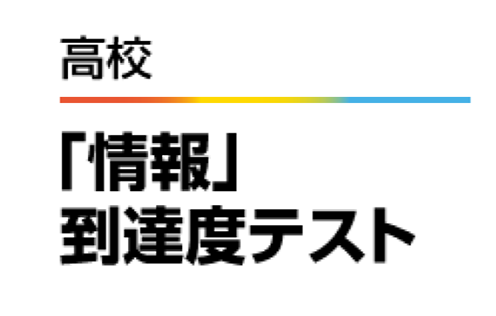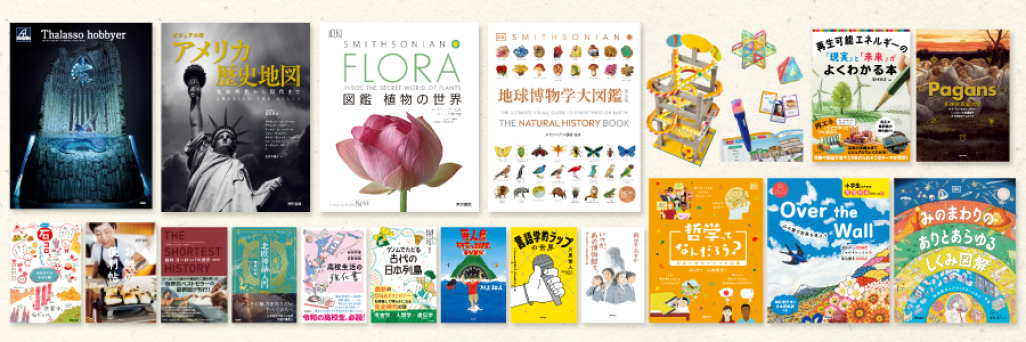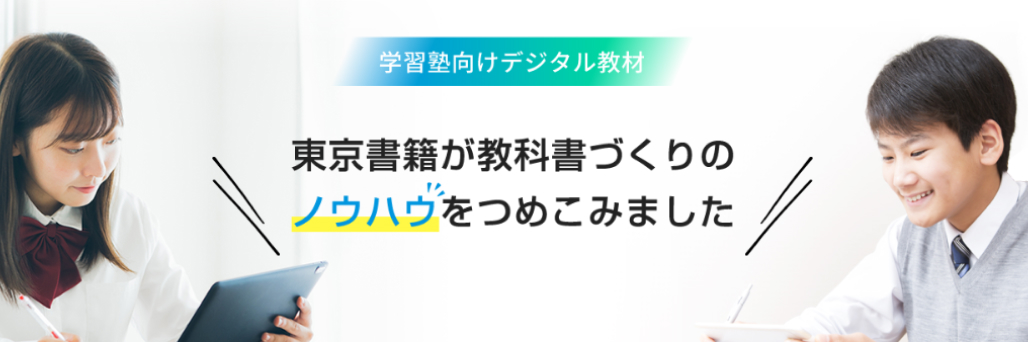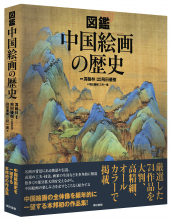
図鑑 中国絵画の歴史
ISBN:978-4-487-81776-4
定価6,600円(本体6,000円+税10%)
発売年月日:2025年08月18日
ページ数:288
判型:B4変形
中国絵画の全体像を編年的に一望する本邦初の作品集!
厳選した74作品を、大判、高精細、オールカラーで掲載!
名画の背景にある物語や伝説、表現の工夫・技法・画家の生涯などを多角的に解説。
数多くの部分拡大図を交えながら、中国絵画の楽しみ方を余すところなく紹介。
=本書の特徴=
・魏晋南北朝時代から清代末期まで長大な中国絵画の流れを74作品で一望
・北京故宮博物院、台北故宮博物院、東京国立博物館、大阪市立美術館、メトロポリタン美術館ほか、各国の博物館の優れた収蔵品を年代別に解説
・なかでも北宋時代の名品「千里江山図」「清明上河図」は圧巻3メートルの片観音製本で紹介!
・執筆および日本語版監修と翻訳は中国と日本の若き俊英が手掛け、中国絵画史研究に新風を吹き込む
中国絵画の全体像を一望する本邦初の作品集!『図鑑 中国絵画の歴史』紹介動画
序文 日本語版監修・翻訳にあたって
世界史の教科書では、世界の諸地域が特色ある文化を形成したことが語られます。近年は超域的な相互関係の記述も増え、ますます広大な範囲を包括するようになりました。その中で中国史は、隣国としての長きにわたる交流から、わが国でも大いに関心を集めています。
しかし、「世界の美術」と言えば、多くの方はイタリア・ルネサンスや印象派の名画を連想するのではないでしょうか。これと並び、琳派(りんぱ)や浮世絵も「日本美術」として広く認知されています。一方、中国史への関心の高さと裏腹に、こと美術の話となると、中国など意識したこともない人が多いようです。兵馬俑(へいばよう)・王羲之(おうぎし)・景徳鎮(けいとくちん)あたりが思い浮かべば、かなり知っている方でしょう。
本来、中国には西洋と対抗しうる美術の伝統があり、西洋とは別の方法で芸術表現の高みに達する可能性を教えてくれます。そして、それは日本美術の前提としても重要です。日本美術の多くの分野はある時代の中国美術が伝わって根づいたもので、その「日本らしさ」は影響元である中国との対比によってこそ鮮明となるからです。
本書は中国絵画史上の主な作品を通史的に見て、その芸術的価値と歴史的意義を紹介するものです。原著の編著者・馮翰林氏は中国の中央美術学院を出て宋元時代の作品研究を発表しており、本書の解説は中国の最新学説を反映しています。対象は絵画に絞られ、書や陶磁器は登場しませんが、中国絵画の主流である山水画を半分に抑え、人物画・花鳥画にも目配りしたバランスの良い配分となっています。
ですが、もしあなたが日本で書かれた中国美術の解説を読んだことがあれば、「あれっ」と思うかもしれません。日本で最高の古典とされた画僧・牧谿(もっけい)は登場せず、日本の寺院に多数伝わる仏画も一点も採録されていません。これらは中国本土の美術史の主流ではないのです。
長い交流史の中で、日本の人々は中国絵画への独特の見方を形成してきました。そのため、日本にある中国絵画は本土のものと全く様子が違います。これらと異なり、本書で紹介するのはまさに本家本元、中国の主流の美術史というわけです。
この翻訳の仕事を頂いた時、私は展覧会の準備に忙しく、本格的に着手するまで半年の時間を要してしまいました。ようやく取り掛かると、本書の解説には漢詩文の引用が思いのほか多く、これらを機械的に訳しても原文が狙ったような効果は生じないことがわかりました。そこで急遽、古典中国語(漢文)の専門家である三村一貴氏に200ほどの漢文引用箇所を中心として共訳をお願いしました。
三村氏は私からみて大学時代の書道部の先輩です。古今東西の数多の言語に通じ、人文的知識に富んだ文字通りの「教養人」としての姿に当時は衝撃を受けたものです。三村氏は本書の引用文を一つ一つ原典にあたり、出典や内容を精査し、最適な日本語に訳してくださいました。
大変なご負担をおかけしてしまいましたが、この作業を通じて本書の完成度は格段に高まりました。
また、企画に携わってくださった東京書籍の小野寺美華氏は、専門用語にルビと語釈を付け、本書をわかりやすい入門書とすべくさまざまな工夫をしてくださいました。小野寺氏のご尽力がなければ、本書は難読漢字だらけの不親切な書物となっていたことでしょう。この場を借りて御礼申し上げます。
美術と歴史を愛する方々が本書を手に取り、中国絵画の奥深い世界に分け入る案内書としてくだされば、訳者として望外の喜びです。
飛田優樹
唐・張萱 搗練図(宋模本)
(伝)五代・黄筌 写生珍禽図
北宋・李公麟 五馬図
掲載した絵画の「鑑賞のポイント」は拡大して解説
明・文徴明 真賞斎図
目次