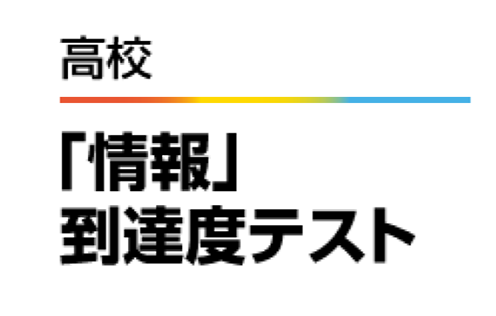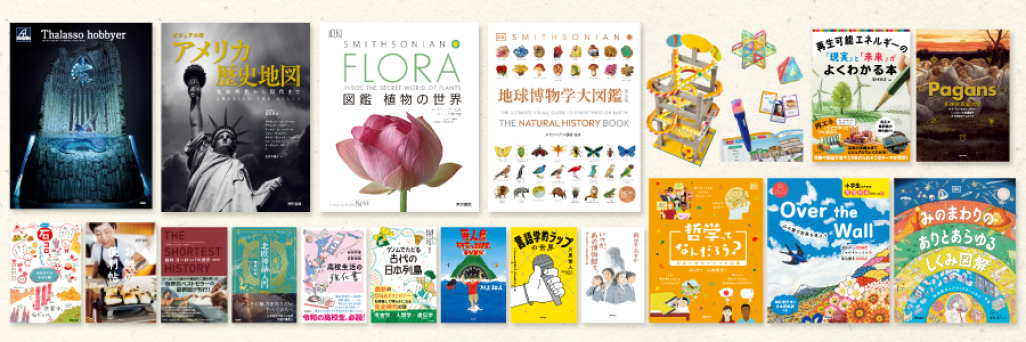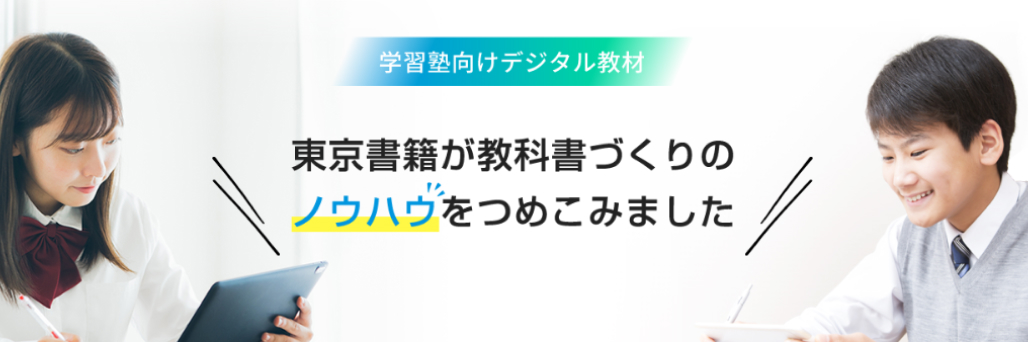大仏師が教える仏像彫刻の深すぎる世界
ISBN:978-4-487-81744-3
定価2,750円(本体2,500円+税10%)
発売年月日:2025年08月18日
ページ数:208
判型:A5
6世紀に日本に仏教とともに伝来して以来、仏像は人々の信仰を受け止めてきた。
仏像は、運慶や快慶などの多数の名仏師・工房によって制作され、その技術や構想は蓄積し、現代まで濃密な伝統を作り上げてきた。
本書は、現代の「大仏師」である江場琳觀が、制作にたずさわる仏師ならではの奥深く新鮮な仏像の見方を紹介するまったく新しい仏像の入門書。
構成は、如来、菩薩、明王、天部などの種類別章構成。
その整理された構造の中で、国宝・重要文化財の仏像、自作の仏像の数々を例に挙げながら、仏像の礼拝、鑑賞・解釈において欠かすことのできない基本要素の紹介に加えて、技法、表現の工夫、制作の意図などの見どころを語りつくす。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「大仏師」とは
それは仏像制作にかかわる仏師たちを主導する長の尊称であり、また知識、技術と芸術性を兼ね備えた最上位の仏師が限られた名刹からのみ授かることにできる尊称である。
仏像の見方が変わる、珠玉の一冊『大仏師が教える仏像彫刻の深すぎる世界』紹介動画
「はじめに ― 仏像彫刻の世界へようこそ」
仏像とは、至極シンプルないい方をすれば、「仏教に由来する礼拝の対象たり得る像」ということになります。
もともとは狭義に、「如来」や「菩薩」の姿の像を仏像と称していました。やがて仏教のアジア全域への発展とともに生み出されていった多くの如来や菩薩、またそれらに加えてヒンドゥー教やその他の宗教から取り込まれた「天(部)」、密教の教義から考え出された「明王」などの表現が、様々な像として展開してゆき、現在ではそれらを含んで「仏像」と捉えるようになっています。また、仏像にはピラミッド型の階層組織があり、如来から、菩薩、明王、天部、羅漢・高僧などとくだっていきます。
仏教が日本に伝わったのは六世紀半ば、朝鮮半島の百済からといわれています。その際に、仏像もともに伝来したと考えられています。日本でも六世紀末ごろから大陸の様式を学びながら作られ始め、徐々に日本独自の展開を遂げていきます。制作方法も、銅で作られる金銅仏、漆を用いる乾漆像、粘土を用いる塑像などによるものから、やがて木彫による制作が主流となっていきます。
こうして、仏教の広まりとともにあまたの寺院に広がった仏像は、時代の変遷とともに表現を変え、時代と世代を越えて人々の礼拝を受け止め、敬われてきたわけです。さらに今日では、文化財、あるいは美術作品という捉え方もされており、仏像への新たな価値観も見出されるようになっています。
本書では、飛鳥・白鳳時代から、奈良、平安、運慶ら慶派が活躍する鎌倉時代、また明治の作例まで、時代や宗派ごとの様式、それらに応えた仏師たちの創意工夫によって生まれた多様な仏像を紹介しています。それぞれは各章の説明に譲りますが、この「はじめに」では、飛鳥時代の飛鳥大仏、仏教伝播の過程をその造形に刻んだ薬師寺の薬師三尊像、庭園とともに国風文化の到達点といわれる平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像、鎌倉彫刻の、なかでも運慶彫刻の成熟期に生まれ、日本のリアリズムと対象の人となりまでも抽出して見せた重源上人坐像などを紹介することで、日本の仏像の流れ・アウトラインを案内したいと思います。
飛鳥彫刻の起点 ー 釈迦如来坐像
飛鳥寺( 安居院/あんごいん)本堂に座す釈迦如来坐像は飛鳥大仏とも呼ばれます。飛鳥寺は蘇我馬子の発願によって六世紀末から七世紀はじめに建てられた日本最古の本格的仏教寺院で、法興寺もしくは元興寺とも呼ばれました。606年に仏師、鞍作止利(くらつくりのとり)(一般に名を知られる最初の仏師)による丈六(じょうろく)(本書176頁参照)の金銅仏が金堂に収められたという記録が残ります(日本書紀)。それが飛鳥大仏です。710年に平城京へと都が移った後も飛鳥寺は本元興寺(もとがんこうじ)として飛鳥の地に残りました。
飛鳥大仏は何度も火災に遭ったようで全身にわたって修理の跡があり、鼻の中央から上と、手の一部以外は全て後世の補作といわれます。しかし、当時の造形が残る杏仁形(きょうにんがた)の眼と額は、鞍作止利の作の銘が残る法隆寺金堂の釈迦三尊像に通じるものがあり、飛鳥彫刻の起点ともいうべき作風を今に伝えます。
仏教伝播の過程 ― 薬師三尊像
薬師寺の中尊である薬師如来は左手に薬壺を持たず、右手は施無畏印(せむいいん)、左手は与願印(よがんいん)を結ぶ古式の薬師如来の姿を表しており、宣字形台座に結跏趺坐(けっかふざ)する丈六の如来坐像です。正しくは薬師瑠璃光如来といい、東方にある浄瑠璃浄土の教主として病気や貧窮で苦しむ人々を救い、心身を安らかにしてくれます。脇侍の日光菩薩、月光菩薩は内側の手の肘を曲げ腰を捻って立つ一丈の立像で、薬師如来坐像を中心とした三尊像の構成は美しいバランスを見せます。三尊ともに蝋型鋳造ですが、鍍金は一部に後補のものを残して剝落し、現在では黒褐色の肌が滑らかな光沢を放ちます。日光菩薩、月光菩薩の、薄い衣に包まれた均整のとれた姿は古代仏像彫刻の白眉としても名高いのです。
薬師如来の座す宣字形台座もまた類例を見ない造形として広く知られます。台座の中段四面に窓のような洞穴のような刳り型があり、その中には裸形の蛮人というか、鬼神のような存在が彫られ、正面中央には柱状の意匠が見えます。框(かまち)にはギリシャ由来の葡萄唐草文様である葡萄の実と葡萄の葉が見えます。また、ペルシャの蓮華文様も描かれ、一番下の框には青龍、朱雀、白虎、玄武という中国由来の四神が描かれています。これは、ギリシャ、ペルシャからシルクロードを経て中国、朝鮮半島、日本へと伝わってきた仏教の、行く先々の文化がこの台座に合流し凝縮して表された造形です。異なる宗教や文明に出会い、しかし、否定し排除するのではなく取り込んでいく。薬師寺の造形には、そうした仏教伝播の過程が克明に表されています。白鳳時代(天武〜持統朝)に制作されたとする説と、平城京遷都後の天平年間に制作されたとする説があるようですが、いずれであっても造形の見事さと歴史的な価値は揺らぐものではありません。
国風文化の頂点 — 阿弥陀如来坐像
薬師三尊像の宣字形台座が伝えるように、多様な地域を経て伝わった渡来仏が、時間の積み重ねとともに日本人の感性によって変化と洗練を加えていきます。その一つの頂点が平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像です。藤原頼通の発願で、1053年に供養された鳳凰堂(阿弥陀堂)の本尊として制作されました。平安時代中期に活躍した仏師定朝(じょうちょう)による丈六の阿弥陀如来坐像であり、現存する定朝唯一の作といわれます。曲線による丸みを帯びた体軀に薄い衣をまとい、柔和な表情を見せる調和のとれた造形は和様の到達点ともいえるものです。像は、正中線と両側で材を矧(は)いだ日本独自の寄木造りであり、体軀全体に内刳りが施された寄木造りの完成形を示し、定朝様式ともいわれ、以降、仏像制作の規範となって多くの寺院で踏襲されました。
建立された平安中期は浄土信仰が盛んな時期であり、平安貴族たちは極楽浄土をこの世に表現しようとしました。庭園は浄土式庭園と呼ばれます。宇治川のほとりに建ち、鳳凰堂を取り囲む阿字池は宇治川の水を引いていました。かつては川に突き出した釣殿があり、舟から直接寺に入ることができたそうです。また宇治川対岸には深い山々が広がり、豊かな水と緑に囲まれた四季を感じさせる浄土のあり方は、かつて仏教伝播の道程の一つであった砂漠にある敦煌の浄土観とは全く別のものだったことでしょう。
鎌倉彫刻のリアリズムと抽象性 ー 重源上人坐像
末法思想と貴族の篤い信仰により、多くの求め(需要)に応えた定朝様式でしたが、一方で模倣や形式的な繰り返しによって彫刻はみずみずしさを失いました。その反省から天平彫刻を規範とした写実性や力強さを求める動きが興ります。こうした動きの中から運慶や快慶ら、のちに慶派と呼ばれる仏師集団が生まれてきます。1180年、平重衡ら平家一門による南都焼き討ちが起き、奈良の多くの寺社が被害を受けます。なかでも興福寺、東大寺の被害は大きく、興福寺は春日社を除いて全焼、東大寺は主要建築物をほぼ失い、鐘楼、二月堂、法華堂など、中心から離れた建造物はかろうじて残りました。
大仏も焼け落ち、大仏復興のために各地を勧進して回ったのがが俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)でした。
重源上人坐像は記録こそないものの運慶が制作に関与し、おそらく没後間もなく作られたと考えられている像です。窪んだ眼窩、左右非対称の目はともすれば視力が弱まっていたのやも、と思わせ、こけた頰、への字に結んだ口は生前の姿を克明に伝えるといわれます。また、側面から見た頭部と胴体の関係などには大胆なデフォルメがあり、抽象性さえ感じられるそれらと、先のリアリズムが同居している点も見逃せません。
東大寺復興の大勧進という二十数年の長きにわたる大事業を成し遂げた傑僧の風格はもちろんのこと、彼の力なくしては成し得なかった事業をともにするうちに築かれたであろう、仏師との間の信頼関係と敬愛、思慕のようなものを感じさせる造形です。私は、そこに施主と制作者が苦楽をともにし、尊敬し合い、互いが互いのために奔走して渾身の仕事をつとめ大事業を成すという、施主と仏師の理想の関係を見る気がするのです。
ここで紹介した仏像彫刻の名作を繙き見つめ直すことは、仏像が遂げてきた変遷を感じ取る手がかりともなることでしょう。
仏教とともに伝来した仏像を理解し、さらに理解を深め、借り物ではない自分たちの表現と呼べるまでに消化し、そして昇華し、和様という独自の様式にたどり着き、寄木造りという技法で生産性までも高め、運慶・快慶ら慶派の登場によって躍動と実在感を像のうちに結実させます。こうした変革に次ぐ変革のうちに仏像は写実を超えたリアリティを獲得するのです。
仏教伝播から現代までの長い造形の歴史は、伝統をかたちづくるものであったと理解されているかもしれません。しかし、一見すると抑制的に見える造形活動においても、新しい表現を模索する眼差しと情熱が絶えず注がれてきたのです。その眼差しと情熱は決して忘れてはならないものです。
日本の仏像の歴史は、他国に類を見ない、実に繊細で多様な美の系譜でもあります。この歴史の上に、現代を生きる私たちが共感し得る表現を添えてゆきたい——。過去の名作と、名作を参照した自身の作品を掲載し、仏師の視点でなるべく平易に著す(解説する)ことによって、現代の仏師の取り組みと、これまでになかった仏像の見方を提示することができれば、これほどうれしいことはありません。
コンテンツ
一 如来の章
二 菩薩の章
三 明王の章
四 天部の章
五 仏弟子、羅漢、高僧の章
あとがきにかえて ー 尾上右近さんの手獅子