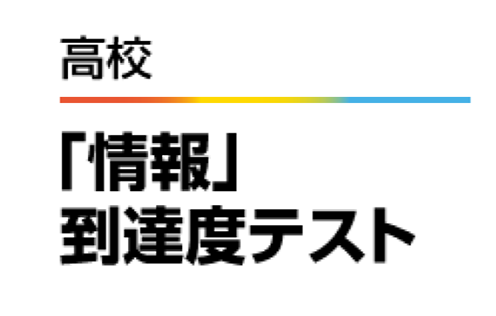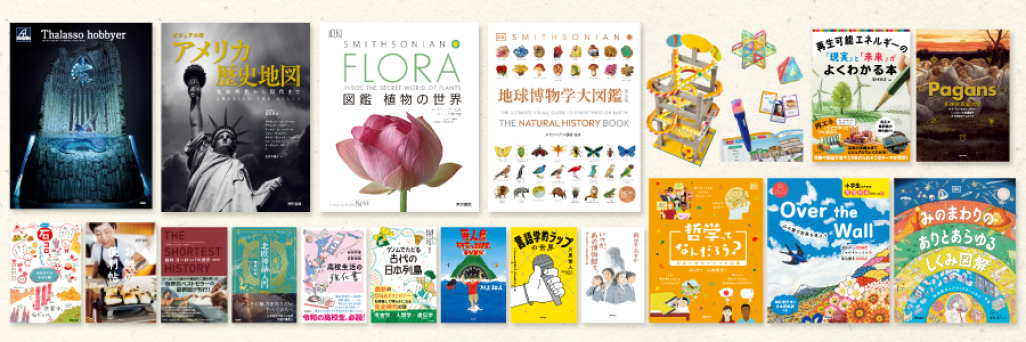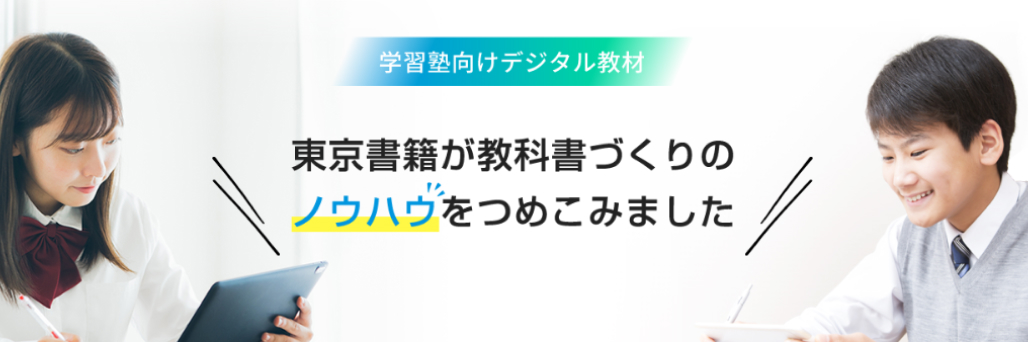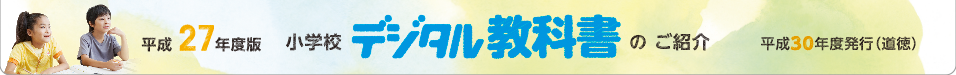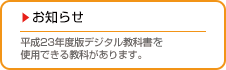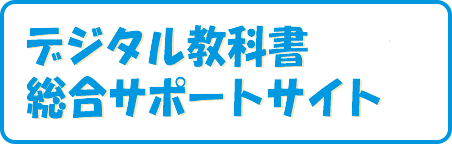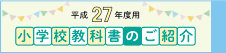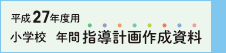|
岐阜大学 教授 益子 典文 教科書は,幾重もの授業の道筋や児童生徒の理解・反応を想定した,厳選された素材の集まりです。また,教科書に配置されている個々の素材一つひとつがどのような力を持ち,どのような制約があるかなど,素材を活用するための手がかりの多くは,厳選された結果であるが故に,教科書の行間に埋め込まれていると言うことができます。よい授業を実践するためには,まず教科書を十分に分析し研究することが重要,とのご意見をベテランの先生方からお聞きします。このご意見は,行間を把握することが重要との指摘なのでしょう。私も,授業づくりを楽しむ鍵は素材の行間を読み解き,様々な工夫を練り,実践してみることにあると思います。 デジタル教科書は,行間の情報を細かく説明する解説書ではありません。サブコンテンツとして組み込まれた,授業設計において多様な発想を支援する「プラスアルファ」の素材群が,教師が行間を読み解く活動を支援し,工夫の可能性を拡げるものであると考えます。プラスアルファの素材には,授業の課題やまとめの内容をさらに深く理解するための素材があります。この素材は,児童生徒が「何に取り組むか」のイメージの共有を促し,多様で個性的な反応を引出したり,複数のアイデアをまとめたりなど,授業展開に沿った思考活動を活性化できます。また,授業中の課題解決進度に違いがある場合には,個に対応するプラスアルファの素材を選択することもできます。 デジタル教科書に組み込まれたプラスアルファの素材の選択肢の拡がりは,先生方の授業設計活動を,より楽しく豊かにできると考えています。 |
 |
東北学院大学 准教授 稲垣 忠 教科書にある写真や挿絵,学習課題などを大きく映して,説明したり子どもたちの気づきを引き出したりしたいときがあります。クリック(あるいはタッチ)すれば,すぐに大きく見せられる。デジタル教科書はとてもシンプルな道具です。 授業での先生方の使い方を調査したことがあります。最も使われたのが,この教科書紙面を大きく映す機能でした。次に使われたのが,教科書にはない映像や資料を見せること。最後に,教科書の本文に画面上で線を引いたり色でマークを付けたり,といったところでした。授業の中で,教師は子どもたちの反応を見ながらこれらの機能を呼び出します。 デジタル教科書を開くと,さまざまなボタンが並んでいます。どんな機能があるでしょうか? どう並んでいるでしょうか? デジタル教科書の開発では,使い勝手(インターフェース)をどう改善できるか議論が重ねられました。迷わず使えるようになっているか,よく使う機能がすぐ手の届く位置にあるか,ボタンの絵柄はすぐ意味がわかるか,確かめてみましょう。チョークや黒板を見て使い方に悩む先生はいません。紙の教科書は指差しすれば指示できます。デジタル教科書は画面上のデザインで使い方を理解する必要がありますが,目指すのは同じことです。 見せたいものを大きく見せられる,子どもたちと話し合いたい教材をすぐに呼び出せる。先生方が目指す授業を実現する「助っ人」として,普段の授業で便利に使ってみましょう。 |
稲垣先生のWebサイト http://www.ina-lab.net/