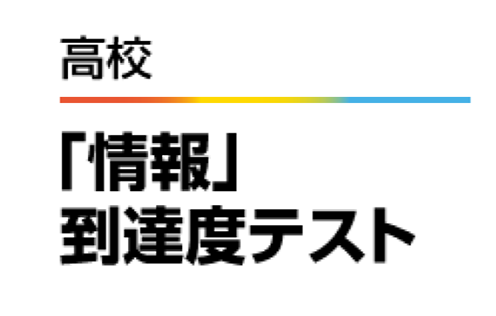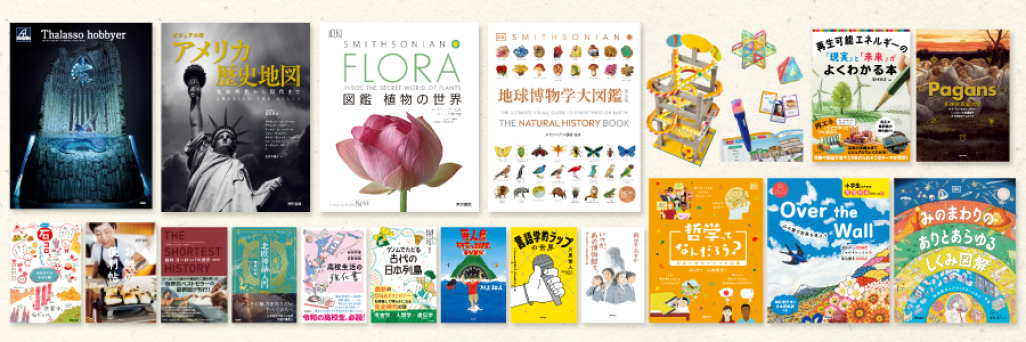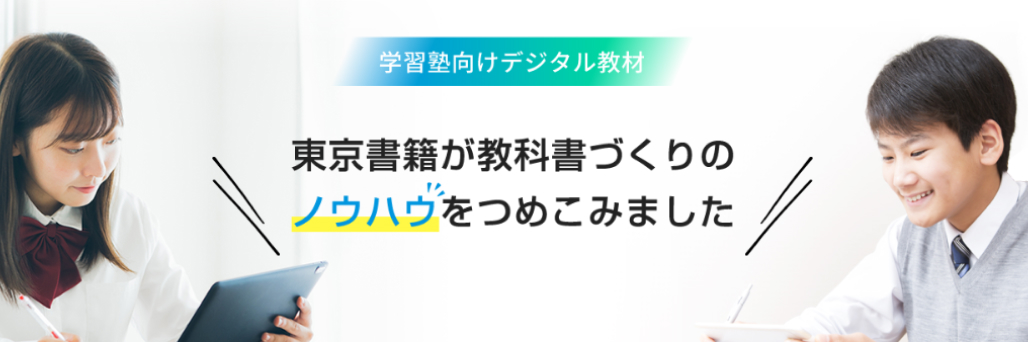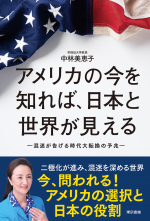
アメリカの今を知れば、日本と世界が見える_オンデマンド版
ISBN:978-4-487-81833-4
定価3,520円(本体3,200円+税10%)
発売年月日:2025年03月12日
ページ数:360
判型:四六
中・印・米の三極時代に日本はいかに進路を見出すべきか。
あと20年も経たないうちに、アメリカ主導の時代は幕を閉じ、世界は中国、インド、アメリカの三極体制へと移行していくだろう。戦後、アメリカに依存しながら成長を遂げてきた日本は、この変化に備え、国内経済の維持・発展を含め、国際社会においていかなる道を歩むべきか。アメリカの内外情勢を軸に、今後数十年にわたる国際社会の動向を見据え、日本が政治・経済両面で進むべき方向性を考察する。
はじめに
2024年の大統領選挙は、トランプ氏の「アメリカ第一主義」の復活を決定づけた。アメリカ第一主義は、過去の歴史的サイクルにおける孤立主義や保護主義の再現に似ていると言うこともできるだろう。このような政策は、1930年代の大恐慌期や19世紀末の工業化時代に見られた現象でもあり、経済的不安と社会的緊張が生じるときにしばしば登場する。
トランプ氏の主張は、グローバル化によって取り残されたと感じる白人労働者階級に訴えたのであり、特に非大学卒の有権者層に響いたとされる。これらの人々は、グローバル市場や技術革新による変化に対応できない自分たちの境遇を訴え、既存の政治エリートに不信感を抱いていたことが既に指摘されている。
しかし2024年の大統領選挙では、トランプ氏が2016年の選挙のとき以上に支持層を膨らませ、民主党と共和党の支持層の流動化現象に至っている実態が明らかにされた。AP通信の Vote Cast 調査によれば、トランプ氏は従来の支持層である白人有権者、非大学卒有権者、高齢者に加え、若年層、黒人男性、ヒスパニック系男性からの支持を拡大したのである。非大学卒有権者の55%はトランプ氏に投票し、ハリス氏の約4割を上回った。また、18~29歳の最年少有権者層でも支持を伸ばし、45歳未満の有権者のほぼ半数を獲得した。 一方、民主党のハリス氏は、都市部の白人大学卒男性からの支持を増やしたものの、他の層での支持減少を補うには至らなかった。特に、ラテン系有権者(特に男性)の共和党支持への傾斜が、民主党の支持基盤の融解を示している。これらのデータは、2024年の選挙において、民主党と共和党の支持層に流動化が顕著になったことを示している。リチャード・ピルデス教授(ニューヨーク大学法科大学院)の研究では、これは徐々に進行してきた現象であり、2024年の大統領選挙で決定的になったという。
もはや「分断」という観察的な視点でアメリカを外から論評する段階は、過ぎつつあるようだ。過去の変革期と同様、2024年の選挙では、社会の分断は固定的でないことが明らかになった。今のアメリカは既に混迷の時代に移り、日本を含む世界の人々をも巻き込んでいく時代の転換期に入った可能性がある。
歴史を振り返ると、アメリカは50年に一度の周期で社会的な混迷と再生を経験してきた。1960年代の公民権運動や1970年代のウォーターゲート事件後の改革は、アメリカが民主主義を強化する契機となった。現在の混迷もまた、アメリカが新たな民主主義の形を模索する過程であると考えることができる。
さらに、2024年の選挙で注目すべき点は、従来の選挙管理や情報操作の課題が新たな形で浮上したことである。AIやブロックチェーン技術を活用した不正防止やサイバー攻撃対策は、選挙の透明性向上に一定の成果を上げた。しかし同時に、ソーシャルメディアを通じた偽情報の拡散や有権者の情報操作という新しい問題が顕在化した。これらの問題は、現代特有の課題であると同時に、過去の歴史の中で繰り返されてきた「不安定な時代における情報戦」の現代版でもあった。
そしてトランプ氏の当選は、アメリカ社会が抱える経済的不平等、価値観の分断、そして国際的責任のあり方を再定義する機会にもなりそうである。過去の歴史を振り返ると、アメリカは常に混迷の中から新しい秩序を見いだしてきた。この歴史的文脈を理解することは、現在の混迷が単なる危機ではなく、未来への転換点であることを示している。歴史を紐ひも解くことで、アメリカの「混迷の時代」がどのように展開し、新たな社会を築いていくかのヒントを得る機会となる可能性がある。
アメリカの歴史には、「大転換」のサイクルが存在するとされている。このサイクルは、内外の要因による激しい変動と、それを乗り越えての再構築によって特徴付けられる。建国の経緯や憲法起草の時代はもとより、南北戦争も19世紀のアメリカを二分し、奴隷制の廃止と国の再統一という形で歴史的な転換点を迎えた。20世紀初頭には産業革命と進歩主義運動が重なり、アメリカ社会は急速に近代化し、労働者の権利や政府の役割について新たな方向性が示された。さらに、20世紀半ばの公民権運動は、社会的平等を求める大規模な変革をもたらし、アメリカにおける人種間の関係性を劇的に再定義した。
これらの転換期に共通するのは、深い混迷を経て、その混迷を乗り越えた先に新たな社会の形が築かれるという点である。現在のアメリカもまた、歴史的な転換期にあるのだろう。トランプ政権の復帰が示すように、国内外での政治的分断と社会的対立が顕著となっているが、これは過去の混迷期と同様、社会全体が新たな方向性を模索している証左とも言える。2024年の大統領選挙では、都市部と地方部、教育水準の高い層と低い層の間での価値観の対立が一層明確になった。しかし、このような分断はアメリカにとって新しいものではなく、むしろ建国以来の歴史を通じて繰り返されてきたテーマである。
また、アメリカが民主主義の「実験国家」としての側面を持つことも、歴史を振り返る中で浮かび上がる重要な要素である。建国当初から、アメリカは人類の自由と平等を基盤とする新しい政治体制を試みてきた。独立宣言や憲法の制定は、その理念の最初の具体化であったが、それを実現する過程では多くの困難が伴った。民主主義の原則を実際の社会に適用するための試行錯誤の連続であった。アメリカの歴史は、こうした努力を通じて自由と平等の理念を拡張していく過程の記録であり、現在のアメリカ社会が直面する課題もまた、この流れの中で位置付けられる。
アメリカの政治は、単なる国内問題ではなく、世界の安定と繁栄に直結する影響力を持つ。2024年の大統領選挙におけるトランプ氏の再選は、アメリカ国内の深刻な格差や価値観の変化を浮き彫りにすると同時に、グローバルな影響力を再確認させた出来事となった。この選挙の結果は、アメリカが歴史的な変革の周期に再び入ったことを示しており、その波及効果は日本を含む世界各国に及ぶと考えられる。トランプ氏は高関税政策を掲げ、国内製造業の復活を目指している。この政策は短期的には効果を見せるかもしれないが、長期的には保護主義がアメリカ経済を閉塞的なものにするリスクも内包している。高関税政策や移民規制の強化は、国際貿易や地政学的安定に大きな影響を与える。中国との経済戦争の激化や移民制限による労働力不足は、アメリカ自身の経済成長を抑制する可能性があるだけでなく、世界経済全体にリスクをもたらす。また、気候変動対策や新技術の開発が停滞すれば、アメリカがリーダーシップを失い、国際社会が持続可能な未来を模索する上での障害となることも懸念される。
しかし一方で、混迷の中には常に変革の種があることを見逃してはならない。AIや核融合エネルギーといった技術革新は、新たな経済成長をもたらす可能性を秘めている。アメリカがイノベーションを推進し、技術を活用して生産性を向上させれば、不平等や気候変動といった課題に対処する道筋が見えてくるかもしれない。この方向性は、アメリカ自身だけでなく、日本をはじめとする同盟国にとっても希望を抱かせるものである。日本にとって、アメリカの動向を理解することは、自国の未来を見据える上で欠かせない。例えば、イーロン・マスク氏らをリーダーに据えた「政府効率化省」は、AIやロボット技術を活用した行政改革のモデルケースとなるかもしれない。これを日本の行政や経済政策に応用すれば、長期停滞を乗り越える新たな可能性が生まれるだろう。また、日本は長年「先送り」によって課題を後回しにしてきたが、アメリカが混迷を通じて変革を実現しようとする姿勢は、日本にも多くの示唆を与える。特に高齢化社会や労働力不足の解決には、AIやバイオテクノロジーを活用した政策転換が必要であり、この点でアメリカの成功例や失敗例から学ぶべきことは多い。
本書は、こうしたアメリカの「混迷の時代」を読み解くために欠かせないアメリカの建国のプロセスや現在の制度およびそこに至る考え方を解説した。そのことによって、アメリカが将来にわたって何を模索し、どのような政治的枠組みの中で葛藤しているのかを理解することができるからである。その際、アメリカの「今」は、過去の蓄積の上に成り立っており、すでに構築された国内の独特な制度と枠組みの中で展開されている事実を忘れてはならない。
そしてアメリカを理解することは、日本や世界にとって極めて重要な視座を提供する。本書が掲げる「アメリカの今を知ることは、日本と世界を知ること」というテーマは、単なる知的探求の意義に留まらず、国際社会における共存と協調の未来を形作る具体的な手段でもある。アメリカという「混迷の時代」を象徴する存在が、いかにして新たな国際秩序を形成し、それが日本や他国にどのような影響を及ぼすかを深く洞察することが求められる時代に入った。アメリカを理解することは、日本を含む世界全体の課題と可能性を理解することにもつながるのである。
2024年12月
中林美恵子
コンテンツ
1 ウクライナ戦争・パレスチナ問題
ウクライナ戦争とアメリカ世論/ウクライナ戦争の戦況で変化するアメリカ世論/アメリカが軍事行動を起こすとしたら?/アメリカの対ウクライナ支援/冷める世論/イスラエルの対ハマス攻撃/民主党・共和党それぞれの対応
2 高進するインフレ
もう1つの課題「経済」/ガソリン価格高騰が貧困層を直撃/バイデン大統領の中東訪問
【第1章 アメリカ合衆国という国の成り立ち】
1 アメリカ合衆国憲法の制定
トランプ前大統領、狙撃される/合衆国憲法修正第2条と銃規制/アメリカ独立と「大陸会議」/「主権ある州」と「連合規約」の成立/「やくざなヤンキー」、「しらみだらけの田舎もの」/妥協の産物としての「連合規約」の限界/「アナポリス会議」での「大会議」の提案/「大会議」開催への険しい道のり/「大会議」は秘密裏に進められた/「バージニアプラン」から「合衆国憲法」へ/「合衆国憲法」/連邦制を明記/「三権分立」/憲法批准とアメリカ合衆国の成立
2 憲法を修正する
権利の章典/基本的人権の保護・人民が武器を保有し、携帯する権利/アメリカ独立記念日頃に集中する銃乱射事件/きわめてアメリカらしい基本的理念/その後の憲法修正/南北戦争と奴隷制廃止/奴隷制禁止とセットの平等条項/禁酒修正条項と禁酒修正条項の廃止/女性の参政権/戦後日本でも女性が参政権獲得
3 アメリカの州と合衆国
ドル紙幣とアメリカ/1ドル紙幣の表面発券銀行/1ドル紙幣の裏面「IN GOD WE TRUST」/1ドル紙幣の裏面国璽/アメリカは西に向けて広がった/連合国家と政府間関係/州は国家のような存在/公選職員で運営される郡(カウンティ)/警察や検察組織を持つ自治体/州が課税権を持つ/州間で企業誘致競争/課税や福祉面での州間競争/州の競争が起きている
【第2章 アメリカの司法と政治】
1 アメリカの裁判所制度
連邦制と三権分立のアメリカ/三権分立と「抑制と均衡」/連邦裁判所と大統領の関係/日米の裁判制度の違い/州裁判所はきわめて身近な存在/アメリカの州裁判制度/地方裁判所と政治/メリーランド州の裁判制度/連邦裁判所(最高裁・控訴裁・地方裁)/連邦裁判所の裁判官は大統領による任命/連邦最高裁判所による違憲審査
2 裁判と政治
司法の場は政治運動の第一歩/ブラウン対トピカ教育委員会裁判/ブラウン判決から公民権運動へ/三権分立の司法と政治/⑴銃規制と憲法修正第2条/⑵人工中絶をめぐる判断/⑶地球温暖化とEPA規制/保守的な最高裁判事を任命/連邦最高裁判所への信頼度は低下傾向
【第3章 連邦議会と二大政党】
1 連邦議会の制度
停止した政府機能/アメリカ国旗に象徴される連邦制/連邦議会は上院・下院の二院制/異なる選出基盤からの選出で権力分散を図る制度/アメリカでは行政と立法が完全に独立している/合衆国憲法の「一丁目一番地」は連邦議会/日本の国会での立法過程・①法律案作成・②閣議決定・③多数決による決定/アメリカの保守とリベラル
2 上院と下院
連邦議会の構成上院と下院/「良識の府」「民衆の府」と連邦議会選挙/上院の「条約承認権」と「人事承認権」/アメリカの選挙権の歴史/有権者登録が必要なアメリカの選挙権/上院の議長は副大統領/議会で多数の議席を占める「多数党」であることが重要/院内総務と院内幹事/移民または移民2世の連邦議会議員/急増する連邦議会女性議員/共和党女性候補が抱えるジレンマ
3 連邦議会議員の仕事
連邦議会では議員はほとんど議場にいない /フロア・マネジャーと少数の議員だけ/議員1人でも法案を提出できる/徹底した委員会中心主義/委員会には大きな権限が与えられている/補佐官が議会活動を補佐/議会補佐官は党派性を持つ/【コラム】事務的な補佐の必要性から始まった補佐官制度/【コラム】議会補佐官の選挙活動/法案の作成と最終チェック/法案を審査対象にするかどうかは委員長が決める/逐条審査および修正案の検討/委員会の報告書/下院では全院委員会から本会議へ/上院での法案審議/フィリバスターという上院ルール/フィリバスターとクローチャー/フィリバスターは依然として有効/【コラム】フィリバスターと「核オプション」/【コラム】『スミス都へ行く』/連邦議会では法案は次々と修正される/同じ法案の内容が上院と下院で異なることもある/両院協議会で最終的な法案を作成/法案の可決と成立までのプロセス
4 変換型議会での予算審議プロセス
劇場型議会ではスキャンダルが追及される/連邦議会は「変換型議会」/連邦議会議員は忙しい/予算編成は連邦議会の重要な仕事/「予算教書」と「予算」/連邦議会での予算審議/予算審議のプロセス/「予算決議」と「歳出法」/歳入関連法案と大統領の署名/つなぎ予算をつくって一時しのぎをする/ガバメント・シャットダウンが起きる/トランプ大統領とガバメント・シャットダウン
5 中間選挙と民主党・共和党
アメリカ国民の議会支持率は低い/党議拘束がかかる日本/連邦議会では党議拘束がかからない/1票の違いがモノを言う/バイデン政権でも「50対50」/統一政府と分割政府/中国関連法案では民主党と共和党が協力/大統領は法律案を提出できないのか/民主党と共和党の政策的傾向の比較/中間選挙の結果を見る/予備選挙の日程や実施方法は州によって異なる/ワイオミング州での予備選挙/州への下院議席配分が変わった/「立法府」の「行政府」に対するチェック・アンド・バランス
【第4章 強大な権限を持つアメリカ大統領】
1 大統領の権限
アメリカ歴代大統領のランキング/『トランプ大統領とアメリカ議会』を上梓/トランプ大統領の4年間/第59回大統領選挙ではバイデン大統領が誕生 /第60回大統領選挙では?/行政権を持つ大統領を国民が選ぶ/大統領制の特徴・大統領と連邦議会の関係/大統領の軍事権限/議会による「戦争権限法」/議論が続く「戦争権限法」/「戦争権限法」をめぐる矛盾と現実/条約締結権と任命権・罷免権/議会に対する大統領の権限/行政命令権と国家元首としての権限/徹底した抑制権の配分
2 大統領になるための資格と任期
大統領になるための資格/大統領の任期/大統領の承継/再選回数の規定
3 ピラミッド型の行政機構
アメリカの行政機構/大統領府とスタッフ/政治任用者とメリット制が混在/大統領令
4 大統領の一般教書演説
一般教書演説とバイデン大統領の後方に座る2人の女性/副大統領はランニングメイト/上院議員席にはキャンディ・デスクがある/2022年3月の大統領一般教書演説/2024年3月の大統領一般教書演説
5 大統領選挙のしくみ
大統領選挙の方法/2016年と2020年の大統領選挙
6 バイデン政権の4年間と2024年大統領選挙・トランプ元大統領の復活
バイデン大統領の支持率/バイデン大統領の支持率低下の理由/アフガン紛争の終結とアメリカ国内の厭戦気分/バイデン大統領の経済政策/民主党の次の大統領候補は?/カマラ・ハリス副大統領/カマラ・ハリス大統領候補/共和党の大統領候補/共和党の中の熱狂的なトランプ支持者/若者はどう思っているのだろうか/2024年大統領選挙トランプ前大統領の復活
【終章 世界の中の日本の役割を考える】
1 思考錯誤する民主主義国家
バイデン大統領が主導した民主主義サミット/民主主義国家の数は減少している
2 日米を中心とした多様な連携
日米豪印戦略対話/インド太平洋経済枠組み/地域的な包括的経済連携協定
3 日本の役割
日本の地政学的位置/日米協力と日本の安全保障/日本にとっての日米関係と世界秩序/難しいかじ取りを迫られる時代