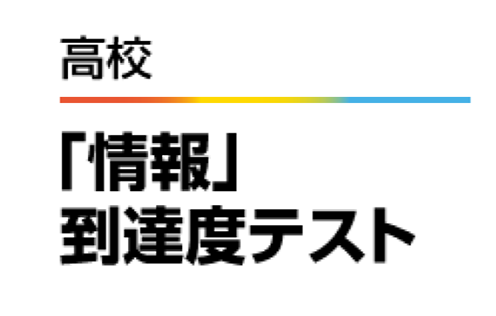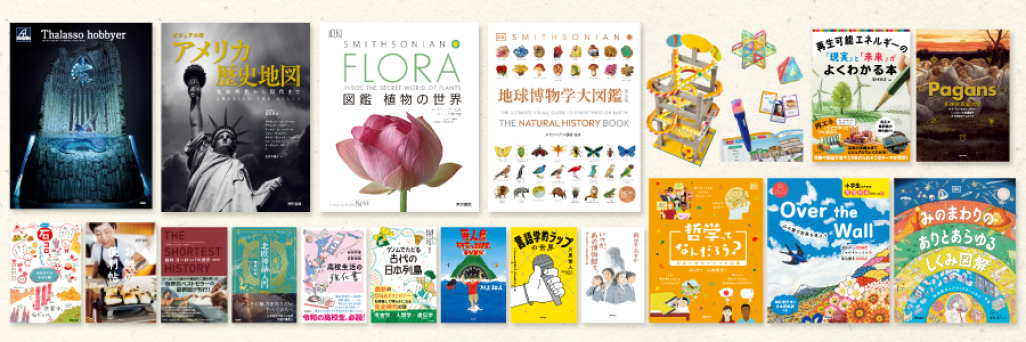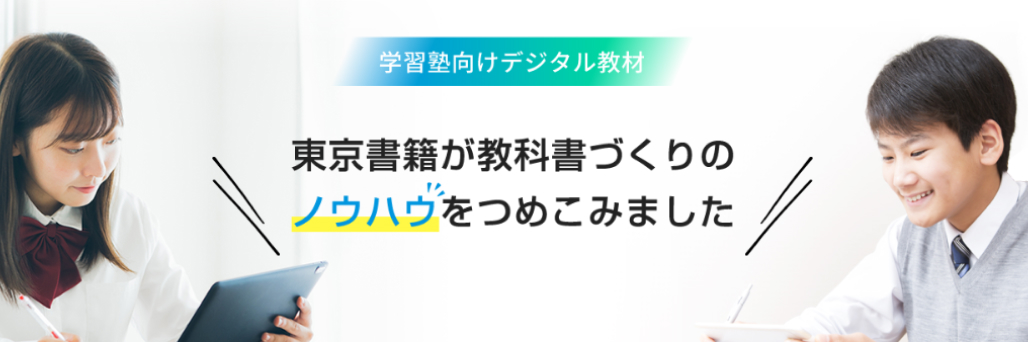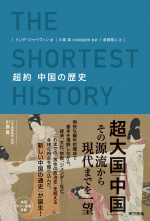
超約 中国の歴史
ISBN:978-4-487-81470-1
定価2,310円(本体2,100円+税10%)
発売年月日:2025年07月01日
ページ数:336
判型:四六判
超大国「中国」 その源流から、現代までを一望
明快な編年的な構成で基本を理解しながら、経済、文化、宗教、ジェンダーなど、これまでの「男性の政治史」を超える多様な視点を織り込んだ、「新しい中国の通史」が誕生!
地図・カラー図版多数
中国の源流から、現代までを一望『超約 中国の歴史』紹介動画
日本語版序文
著者リンダ・ジャイヴィン―マルチタレントな中国研究者
本書は、The Shortest History シリーズの一書であるLinda Jaivin, The Shortest History of China , Black Inc., 2021. を日本語訳したものである。一読すればわかることだが、日本で一般的に手に取ることができる中国通史と比べると、多くのきわだった特徴を持つ著作になっている。
著者であるリンダ・ジャイヴィンは、1955年生まれで、オーストラリア在住の作家、中国語の翻訳家であり、また同時に中国研究者でもあることで知られる。ブラウン大学で中国研究を学び、その後台湾、香港に留学、またこれらの地で働きながら、そして帰国後にも多様な著作を公刊してきた。その関心は多岐にわたり、文学や芸術から政治にも及んでいる。その中国観察についての代表的な著作は、Linda Jaivin, The Monkey and the Dragon: a True Story About Friendship, Music, Politics & Life on the Edge , Text Publishing, 2000. であろう。この著作は、リンダ・ジャイヴィンの中国、台湾、香港などと関わってきたことを踏まえた回想、自伝、旅行記であり、そこには人間関係から芸術論、あるいは政治への風刺も含まれている。この2000年の著作で取り上げられている人物、例えば台湾から中国に亡命しながらも、天安門事件の最前線に立ってハンガーストライキを行い、事件後に台湾に送還された侯徳健などは、本書でも登場することになる。
このある意味で稀有なマルチタレントである著者が編み出した中国の通史が本書である。では、本書にはどのような特徴があるのだろうか。
本書の特徴―社会、思想、女性
本書の章構成は、中国史の叙述の方法としてはオーソドックスな断代史、つまり王朝の時代ごとの通史になっている。しかし、その内容には大きな特徴がある。それは、第 一に中国通史の叙述に見られがちな、「男性の政治史」、あるいは「漢族の男性の政治史」という常識を覆そうとしている点だ。それだけに、本書では漢族以外の多様な主体にも注目しつつ、また男性だけでなく女性も多く登場し、そして政治史だけでなく、経済や社会、文化、宗教、ジェンダーなど多様な側面をも包摂した総合的歴史叙述になっている。
第二に、そのような多様な存在を主人公とし、多様な側面から歴史を叙述することによって、中国社会が元来有しているはずの多様性、活力、ダイナミズムを、漢詩や古典、そして多様なエピソード、さまざまな個人の視点からも描き出そうとしている点だ。これは、中国を一君万民体制として皇帝や指導者ばかりに注目する歴史観とも、また生産力に注目したマルクス主義的な社会経済とも異なる。
第三に、中国の現在の、そしてこれからの政治社会状況を考える上での、多くの歴史的な示唆を意図的に提示しようとしている点だ。習近平と明の朱元璋とを比較してみたり、あるいは中国が歴史的に栄えてきたのが唐代のように開放的な時代であるといった叙述には現状への強い批判的な視線が見て取れる。
第四に、中国が現在国土として主張している領土、領域の境界については疑義を呈しながらも、本書が諸民族の歴史、香港、新疆、チベットなどの歴史も叙述に含めようとしている点が挙げられる。これもまた、本書が「漢族の男性の政治史」を克服する上で重要な要素だろう。
本書には、中国に関する著者の「教養」がふんだんに盛り込まれている。中国古典の素養、古典小説理解、中国の歴史書に散りばめられた様々な寓話、そういったものが数多く織り込まれているのだ。それが本書の内容をより豊かにし、また躍動感を与えるものとなっている。是非多くの読者に手に取っていただいて、マルチタレントな稀有の中国研究者、リンダ・ジャイヴィンの世界を体験してもらいたい。
本書の翻訳にあたって
最後に本書の翻訳について読者にいくつかお断りをしておきたい。翻訳にあたって、もちろん原文を尊重することが大原則であるが、明らかな事実関係の誤認などについては、史実に即して修正した(例えば清朝滅亡年について、1911年を1912年と修正するなど)。無論、歴史解釈や評価などの面で、日本などで言われていることと大きく異なっていても、原文をそのまま訳出した。なお、原文が英語で英語圏の読者に対して書かれていたこともあり、日本語の読者には必要とは思われない箇所については(ごく僅かだが)削除した。なお、中国古典、小説からの引用などに際して、もしそれらの日本語訳が公刊されている場合には、そこでの訳に従った。
日本語版監修・監訳者
川島真
はじめに
中国には「面白い時代に生きて下さい(*訳註) 」という呪いの言葉があるとされるが、実際のところ、そのような言葉はない。とはいっても、中国は「面白い時代」に事欠かない。中国の歴史は、通常の人間のスケールをはるかに超える人物、哲学論議、政治的陰謀、軍事抗争、社会的混乱、芸術上の発明と技術革新にあふれている。中国の歴史はねじれながら前進し、曲がり、飛躍し、後退する。中国の歴史記録は長くて深く、少なくとも今から3500年前にまでさかのぼる。その本質と教訓は、傷と勝利の記憶とともに、現代中国の人々の生活・言語・文化、そして政治の奥底に息づいている。国際場裡で高まりつつある中華人民共和国の重要な役割は、この国の歴史を知ることを必要不可欠にする。なぜなら、それこそが現代中国を理解する鍵だからである。
一例を挙げよう。中国共産党(CCP)は香港、チベット、新疆(しんきょう・シンチアン)ウイグル、南シナ海の島々を中国の領土であると強硬に主張している。その「再統一」への執念の根底には、19世紀に中国がこうむった帝国主義的な欧米列強による屈辱と半植民地化、そして20世紀に起こった内戦がある。それにはまた、2000年前に群雄割拠して世が乱れた時代のことも影響している。はるか昔のことながら、乱世の記憶が中国人の深層心理に深く刻み込まれているのである。紀元前221年、中国史上初めて天下統一が果たされ、度量衡と統一書体( 小篆・しょうてん)の大々的な統一が実施された。しかしこれらの統一は専制的な権力者によって強引に行われたものであり、この国の歴史の複雑な一面をうかがわせる。
中国は何ごとにおいても巨大なスケールになる。現在の人口は世界最大規模の14億人以上を誇る。これは世界の人口のほぼ5人に1人が中国人であることを示す(しかも、ここには中国本土以外の土地で暮らす4500万人の中国人は含まれていない)。930万平方キロメートルの面積を持つ国土は、ロシアとカナダに次いで世界で3番目の大きさであり、14の国と国境を接している。中国は世界最大の貿易国、世界第2位の経済大国であり、世界の工場にして、対外的に強硬な軍事大国であり、その陸軍は世界最大である。そして国際機関や外交の世界において中国の役割は着実に大きくなっている。
中国政府がアフガニスタン、エクアドル、バーレーン、ブルガリア、エチオピア、ベトナムなど世界の幅広い地域で進める、総額1兆ドルの「一帯一路構想」は、歴史上最も野心的な国際的インフラ構築プロジェクトである。国内の事業計画も負けず劣らず歴史に残る大規模なものが多く、巨大なダムの建設、国内監視システムの構築、香港–珠海(しゅかい)–マカオを結ぶ全長55キロメートルの世界最長の海上橋、港珠澳(こうじゅおう)大橋の建設などを行っている。さらに中国は人工知能、グリーン・テクノロジー、通信ネットワークのインフラ整備におけるリーダーであり、2050年には科学と技術面で世界一になるという目標を定めている。
中華人民共和国の台頭は世界からさまざまに注目されることになった。そこには政治動員工作も含まれている。人権に関しては西欧諸国とは異なる定義をもつ、とする北京の主張に中国の人権活動家は納得していない。中国共産党は14億人の中国人民を代表して発言しているというが、この広大な国土に暮らす人々が常にさまざまな立場の知識、哲学、政治思想、文化を包摂してきたのは歴史を見れば明らかである。
中国はあらゆる分野において多様である。全人口の90パーセントにあたる人々は漢民族(漢人)であることを主張しているが、それ以外にウイグル人、モンゴル人、チベット人など55もの民族が存在している。〔その非漢族の〕多くは、強い漢化への同化圧力にもかかわらず、固有の言語を話し、独自の宗教的・文化的な慣習を保持している。漢民族もまた、地域ごとに異なる文化やサブカルチャーで自分たちを識別することがあり、上海語や広東語など各地で話される方言は、互いに何を言っているか理解できないほどかけ離れていることさえある。広東語は6200万人以上のネイティヴ・スピーカーがいるといわれ、これはイタリア語の話者よりも多い。公用語の「普通話(プートゥンホワ)」( 英語ではマンダリン〔北京官話〕と呼ばれる)は人工的に作られた言語である。2013年、中国の教育部〔日本の文科省に相当〕は、普通話の普及を政策に掲げているものの、いまだネイティヴ並みに流暢に話せるのは全人口のわずか10%にすぎず、ほとんど話せない国民が全体の30%におよぶことを認めている。
華北人は小麦を好み、華南人は米を好むという傾向はあるものの、常にそうであるとは限らないし、唐辛子など触ったことがないという人々がいるかと思えば、唐辛子なしの料理など作れないという人々もいる。上海人は商売人ばかりでけちだ、と北京人が文句を言えば、北京人は大らかな性格だがそのぶん粗雑だ、と上海人が言い返す。中国人の多様性を前にすれば、典型的な中国人のイメージはあっさりと崩れ去る。中国人の市民の中には、食べるのがやっとの貧しい農民、ジェット機で世界を駆け回る億万長者、仏僧、ナイトクラブのオーナー、熱心なフェミニスト活動家、家父長制の下にあるような「族長」、前衛芸術家、航空宇宙エンジニア、ヤクの牧畜民、映画アニメーター、民主活動家、そして忠実な共産主義者などがいる。彼らの住む家は、高層マンション、2000年前のデザインを模して建てられたコートハウス、ヨーロッパ・スタイルの広大な庭付きの邸宅、長屋、高床式住居、ゲル、さらには居住用に改造した洞窟までさまざまである。彼らの趣味は京劇、西洋オペラ、パンクロック、喉歌(のどうた)〔喉を詰めた発声で歌う特殊な歌唱法。モンゴルのホーミーなどが有名〕、香港ポップス〔ホンコンにおける広東語ポップスのこと。転じてホンコン・ポップスとも言われる〕、中国将棋、テレビゲーム、韓流ドラマ、書道、写真、社交ダンス、扇子などを手に踊る秧歌(ヤンゴー)などなどさまざまあり、これらすべてに通じている人もいれば、どれにも興味がない人もいるだろう。
中国を構成する23の省と5つの自治区( 広西壮(コワンシーチョワン)族自治区、内モンゴル自治区、チベット自治区、寧夏回(ニンシアホイ)族自治区、新疆ウイグル自治区)はそれぞれ高度に都市化されている。ただその都市化された空間も、凍った草原地帯から熱帯の島々、ジャングル、砂漠、肥沃な農地、高山地帯、低氾濫原まで、中国に住む人々に負けず劣らず多様だ。中国のいくつかの都市は、地球最大規模の人口の多さを誇っている。省と同格の自治体( 直轄市)が4つあり、人口数でいえば1位が3000万人を超える重慶で、これに2600万人強の上海が続く。世界で3番目の長さの長江( 揚子江)を別にすれば、アジアの6つの主要河川がチベットに源を発している。それがインダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川、イラワジ川、サルウィン川、メコン川である。大河上流のダム建設、鉱山開発、灌漑計画、さらにはチベット高原の植林まで含めたそれらすべてが全人類の約半数の水の安 全保障に影響を及ぼしている。2020年9月、国連に対して習近平(しゅうきんぺい)国家主席は2060年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「カーボン・ニュートラル」を目指すことを約束したが、これが本当に実施されれば、気候変動を食い止め、この惑星の未来を変える力になるかもしれない。
かつて孔子(こうし)(前551~前479)に向かって一人の弟子が、政(まつりごと)を任されたらまず何をしますかと尋ねた。すると孔子は答えた、「名を正す」と。そして説明を続けた、「名が正しくなければ、ことばも順当でなく、ことばが順当でなければ、仕事もできあがらず、仕事ができあがらなければ、儀礼や音楽も盛んにならず、儀礼や音楽が盛んでなければ刑罰もぴったりゆかず、刑罰がぴったりゆかなければ、人民は〔不安で〕手足のおきどころもなくなる 」(金谷治訳『論語』子路第十三)。
ヨーロッパの言語で初めて中国を指すChina という単語が登場するのは、16世紀のスペイン語文献である。この単語は古代の秦王朝(前221~前206)が由来で、サンスクリット語のचीन(チナ)と日本語の「支那」(シナ)を経由して伝わったらしい。当の本人たちは自国を、中國(簡体字で「中国」、これについては後に詳述する)(Zhōngguó ヂォングォ)と呼ぶのが最も一般的である。この呼び方は3000年前にまとめられた古代の詩集『詩経(しきょう)』にまでさかのぼる。最初の文字「中」Zhōng は「中間」または「中央」を意味する。次の文字「國」Guó は、真ん中に、人々を表す「口」kǒu(くち)があり、その周りに防御を意味する戈(ピッケル状の長柄武器)gē が置かれ、さらに周りを、囲いを示す口部wei が覆っている。國はもともと城壁都市を意味していたが、やがて王が統治する国の意味になり、そして最終的には中華人民共和国のような国家にも用いられるようになった。英語では中國を「ミドルキングダム(中王国)」と訳すことが多々あるが、本来、この中は、王国や都市の中心を指す言葉であって、王国自体が世界の中心に位置するというような意味合いはなかった。
中国語には、いわゆるChina を表す一般的な名称がもう一つある。それが中華(Zhōnghuáヂォンフゥア)である。華Huá は、素晴らしさ、輝き、繁栄などを意味するとともに、古代黄河流域に定住した二つの古代部族のうちの一つでもある。漢民族は自分たちを華族の末裔と称している。「中華」は特定の領土というよりは、神話、伝説、歴史、文化上の概念を含めた中国文明の領域というニュアンスが強い。そのため、中華圏といえば、中国本土や台湾・香港のみならず、キャンベラからクアラルンプール、シンガポールからセネガルにまでいたる、世界各地の華僑(かきょう)社会まで含めることもある。これ以外にもChina を表す言葉はあるが、「チャイナ(China、中国)」という概念は「中國」と「中華」の間のどこかに存在している、と考えるのが妥当なところだろう。この本に登場する略地図は中華人民共和国のものではなく、現在または過去のどこかの時代に「中國」または「中華」と認識されていた地域のものである。
歴史の大部分において、人々は自分たちのことを「中国人」というよりも、その時々の王朝の人間―例えば唐王朝の時代なら、唐人と認識していた。この国の名前にChina が含まれるようになるのは、1912年、辛亥革命により最後の王朝である清が滅んだ後のことにすぎない。1912年に成立した中華民国と、1949年に成立した中華人民共和国は、自分たちの国China を表す際に、ともに「中國」ではなく「中華」を採用した。
孔子はまた、語る資格を持つ者をはっきり示すために、「名を正す」という原則を立てた。私が中国の歴史と言語を学び始めたのは40年以上前のことであり、以後、中国本土、台湾、香港のいろいろな場所で暮らし、旅して回った。私は中国人ではないが、古い中国の歴史家の劉昫(りゅうく)(887~947)の言葉に強く励まされた。劉昫は歴史を書くに当たって大切なことを、将棋にたとえてこう言った。「当事者は正確に判断できないが、傍観者は正確に判断できる」(白水社『中国語辞典』)。
中国の多くの歴史的な出来事とその当事者をめぐってはさまざまな論争が渦巻いている。孔子はものごと全般において節度( 中庸)を求め、厳格な階層社会を奨励した。孔子の理想は中国文明に安定と継続をもたらしたのだろうか、それとも中国の進歩を阻んだのだろうか。中国の思想家たちは何千年もかけて孔子の理想について熱い議論を重ねてきた。私は公平な表現に務めることに最善を尽くしたいし、または少なくとも、こうした問題やそれ以外についても、多様な視点が存在することを記しておこうと考えている。一部の読者は、本書が政治的に不適切であるとか、政治批判であるなどと感じるかもしれない。しかし、私は私の知り得る限りの歴史的事実に忠実でありたい。
中国語は声調言語である。話し言葉は声の高さの高低で意味が変わってくる。本書〔原書〕において中国語の単語を拼音(ピンイン)( 漢字発音のアルファベット表記法)で書く場合、初出の際と索引では「四声(しせい)」を示す符丁を付けてある。なお索引には本来の漢字も合わせて記載されている〔日本語訳では本文・索引ともに、原則的に常用漢字を用いた〕。
拼音はヨーロッパの言語を話す人々にとっては比較的わかりやすい発音のガイドだが、いくつかの「癖」がある。Xは(例:Xi Jinping 習近平のX)英語のshe のsh のように発音する。Cは(例:Cáo Cāo 曹操のC)its のts のように発音する。Qは(例:Qin dynasty 秦王朝のQ)cheese のch のように発音する。Zhは(例:Zhōu Ēnlái 周恩来のZh)jのように発音するが、舌は口蓋につけて丸める。そしてZは(例:Zūnyì 遵義―貴州省内の地名―のZ)はadds のds のように発音するのである。
1949年に中国共産党が政権を握ったとき、読み書きができたのは全人口の4分の1以下だった。識字率を高めるために、共産党政府は基本的な読み書きに必要な2000から3000の漢字を含め、よく使われる1万字の多くを簡略化した(簡体字(かんたいじ))。本書〔原書〕において1949年までの記述には古くから使われてきた複雑な漢字(繁体字(はんたいじ))を、1949年以降の記述には簡体字を用いている。ただし現在も繁体字が使われている香港と台湾はその例外とする〔日本語訳にあたっては、原則的に常用漢字で表記した〕。
中国人の姓は名前の先に来る。芸術家の艾未未(アイ・ウェイウェイ)の姓は艾、古代の歴史家・司馬遷(しばせん)の姓は司馬である。学者・作家・皇帝らは、通常、生涯にわたり、複数の名前や肩書をもっていた。混乱を避けるために、私は皇帝については、最も一般的で誰か明確にわかる年号による呼び方〔例えば清朝の六代皇帝、愛新覚羅弘暦(あいしんかくらこうれき)なら、乾隆時代の皇帝なので乾隆帝(けんりゅうてい)〕を、異なる階級の側室には妃を、作家に言及する際にはそのペンネームを採用することにした。
中国(China)という名詞と「中国(の)」(Chinese)という形容詞〔的用法〕は歴史的・文化的な意味で「中国」を表現する際に使った。「唐王朝の中国」「中国書道」などがその例である。「本土」は1949年以降、中国共産党が直接支配している中国世界の中の部分としての「中国本土」を示している。「香港」は、香港島・九龍・新界を含む、正式に中華人民共和国の香港特別行政区として認められている地域を示すものとする。「台湾」は正式には中華民国と呼ばれる地理的・政治的実体のことだが、中国共産党はここを中国台湾省と呼ぶことを主張している。
このほか、英語では「万里の長城」と「シルクロード」をGreat Walls とSilk Roads と表記するが、末尾のsはタイプミスではない。万里の長城は、さまざまな時代に建設された、不連続の、時には平行する要塞設備の総称である。同様に古代の絹やそれ以外の商品の交易ルートはいくつもあった。例えば最初に茶が栽培された中国西南部には「茶馬古道」が走っていた。
「短くまとめた歴史書」(The shortest history)を書く際に、頭のいい人なら、鍵となるいくつかのテーマや人物に絞り込んで執筆するだろう。私はそこまで賢くない。私は、重要な人物、経済および社会的発展、軍事史、芸術や思想の潮流から何を選ぶか選択を迫られ、結局すべてを選んだ。だが本書で光をあてるテーマ、出来事、人物は、私が当時の時勢をよく表し、中国文化の進化、国家の本質を明らかにすると思うものだ。私は、中国歴代の皇帝、反乱者、思想家、芸術家、異端児、発明家、政治家、詩人、風刺家の名前を網羅していない。本書で私は、最も影響力のある、あるいは最も面白いものの一部を紹介した。そして、この限られたページ数の中で可能なかぎり、彼ら/彼女らの口で語らせている。読者は古代の歴史家、現代の政治家・詩人・風刺家の作品を参照しつつ読むことになる。もちろん歴史は男性のものだけではなく、女性のものでもある。本書では他の一般的な歴史解説書より少しばかり多くの女性に出会えるだろう。
中国は「多元的」だ。その収拾がつかないほどの複雑さこそ、中国の偉大さの一部なのである。
リンダ・ジャイヴィン
*訳者註
May you live in interesting times. は英語圏では伝統的な中国の呪いとみなされている。一見、祝福のように見えるが、皮肉または呪いの表現として使われる。「お前など、面白い時代に生きているがいい」といったところか。「面白くない時代」は平和な時代であり、「面白い時代」は乱世を指すからである。しかし実際には、中国にこの原典にあたるものはなく、19世紀のジョゼフ・チェンバレンの演説が間違って伝わったという説がある。
コンテンツ
第1章 起源―ある卵の孵化、ある文明の誕生
第2章 周―理想の統治から戦国時代へ
第3章 秦—統一・専制・天下
第4章 漢―陰謀、革新、短い空位時代
第5章 大分裂―三国、二人の女性戦士、七賢人、五石散
第6章 唐―黄金時代から永遠の悲しみへ
第7章 宋—最初の社会主義者、朱子学者、都市生活
第8章 元―「栄光の殺戮者」から壮麗な都市まで
第9章 明―栄華と没落
第10章 清—近代にいたるいばらの道
第11章 中華民国―大きな期待とひどい裏切り
第12章 日本の侵略と内戦―共和国の瓦解
第13章 毛沢東の時代―革命の継続
第14章 鄧小平の改革―繁栄と不満
第15章 習近平の新時代―戦狼の台頭