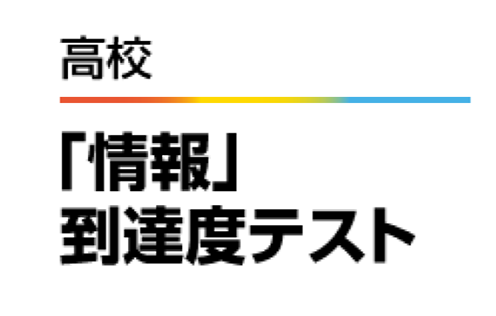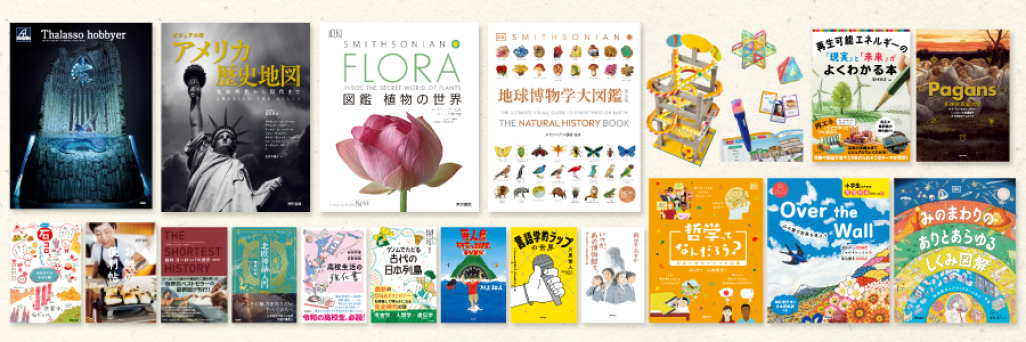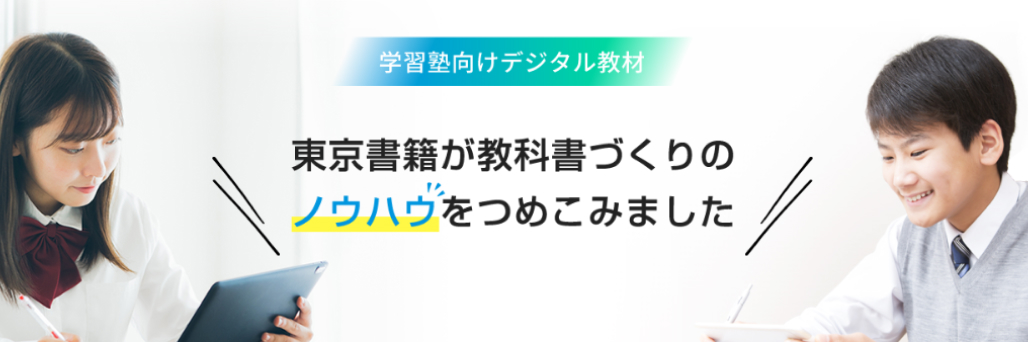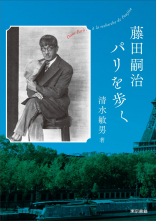
藤田嗣治パリを歩く
ISBN:978-4-487-80789-5
定価2,200円(本体2,000円+税10%)
発売年月日:2021年08月27日
ページ数:232
判型:A5
フジタとめぐる、フジタをめぐる、「エコール・ド・パリ」15日間の旅。
20世紀前半、ピカソやモリディアーニなどとともに「エコール・ド・パリ」のど真ん中で活躍した日本人画家・藤田嗣治。
パリ留学時代にフジタの絵画と出会った第一人者が半世紀を経て、いま改めて藤田の足跡を訪ねる。
パリと郊外のアトリエ、最期を迎えたチューリヒなど藤田にゆかりのある街に赴き、暮らした家や制作現場であるアトリエ、仲間と議論したカフェなどを訪ね歩く。
当時の面影が強く残るパリの美しい街並みの写真も多数掲載。
藤田にとってのパリを追体験しながら、パリへの慕情が募る、もう一歩深く楽しめるガイド。
チューリヒにて ―― 序にかえて
ある年の1月早々のこと、下旬に開催されるダヴォス会議に集まる清華大学の学長やジョージ・ソロス氏を囲む夕食会に参加しないかという友人からの誘いがあった。
ダヴォスといえばチューリヒに近い。かねてから1月下旬のチューリヒを訪ねたいと思っていた。それは私が長年研究してきた藤田嗣治がチューリヒで亡くなったのが1月29日だからだ。チューリヒには何回も行っているがいつも夏だった。そこで冬のチューリヒに行くことを考えてダヴォスでの夕食会に参加することにした。
ダヴォスは雪深く道路もツルツルに凍っていたがチューリヒにはほとんど雪がなかった。道の吹き溜まりに溶けた雪が黒くなっている程度だ。山岳地ダヴォスとはだいぶ異なる。
スイスが山岳の地と思うのは間違いで平地の国だ、と思う。山岳が注目されるようになったのは啓蒙主義の時代に言語学者ソシュールの祖先が山岳の文化に関心を持って以来のことにすぎない。チューリヒもバーゼルもジュネーブもヨーロッパと地続きだ。決して山岳の中の孤立した街ではない。
文献には藤田はチューリヒの州立(canton)病院で亡くなったとある。チューリヒの州立病院とはチューリヒ大学の付属病院のことだ。チューリヒ中央駅から歩いて行けるところにある。ただし坂を登って行かねばならない。チューリヒには何回か来たことがあるので土地勘はある。
丘の上に立派な建物がある。病院の入口を見つけて受付で用件を伝えた。病棟がいくつもありどの病棟なのか皆目検討がつかない。病室から湖が見えた、という記述があることを思い出しそのような病棟はどこか、と尋ねたが受付は困惑するばかりだった。
しかし丘の上の病院なので湖は見えるはずだ。そこでひとつの病棟に入れてもらい屋上に出た。湖を遠望した。
天気も良く風景が輝いている。清涼な微風が頬を洗う。一月も末なのにそれほど寒くはない。凍てついたダヴォスとは大違いだ。こうした日に藤田は他界したのだろうか。死を見とった海老原喜之助によれば病魔の苦痛も感じないのか穏やかな死に顔だったという。
パリの病院ではなくなぜチューリヒの病院だったのか。藤田の日記や文献を精査すればどこかにその理由が記されているかもしれない。チューリヒはパリに来た当初に支援してくれたあのゼーホルツァーの故地だ。ゼーホルツァーはとうに亡くなっていたがその縁者との関係が続いていたのだろうか、などと考えながら病院を辞し湖に向かった。
丘を下り川が湖に注ぐところに開けた広場に出る。その周辺は公園のようになっている。湖の岸辺も陽だまりが暖かかった。湖の周辺を散歩する人、湖を眺めている人。白鳥が寄ってくる。穏やかな午後だ。ここに日常の平和な風景がある。
しかしこうして藤田が死を迎えた時と同じ1月下旬にチューリヒを彷徨していると藤田の不在が強く感じられる。喪失感といったほうが良いかもしれない。しかしその喪失感は不思議と存在感と表裏一体に成っている。
藤田の居た土地を訪ねると藤田に近づけるような気がする。藤田が眺めた風景を体験することで新たな思いが浮かび上がる。紙上やデジタル画像で知った知識は現場で補強され修正される。
絵画とは画面上で終わるのではなく、その背後に膨大な空間が広がり、精神世界がある。
パリのカンパーニュ・プルミエ街で藤田の隣人だったイヴ・クラインは、絵画は背後の空虚、つまり非物質世界への入口に過ぎない、と言っていた。絵画がそうした非物質の世界とこの物質的世界との間の蝶番のような存在だとしたら、藤田が確実に居た場所、つまりこの世の側もできるだけ見ておくことは無意味ではないだろう。
藤田のことを調べ始めたのはパリに留学した1980年頃のことだった。それ以来長年気にかけてきた画家だ。多くの絵を見てきたが藤田に会ったことはない。藤田の作品を見ることを通して「藤田」像を作り上げてきた。私の藤田研究の目的は藤田が求めていたリアリティを絵画そのものを通じて探求することであって、事績を調べることで知識を深めるのはそのリアリティに近づくための手段でしかない。リアリティは知識そのものにはない。
長年にわたって「藤田」像を追っていると「藤田」像とは藤田という画家が描いた絵画の総体としてあるとつくづく思う。つまり生きた人間としての藤田が描いた絵の全てが「藤田」という非物質的な概念を形作っている。
画家としての藤田の居た場所を訪ね歩くことは、非物質的になってしまった「藤田」をこの物質的世界に取り戻す作業なのだ。藤田という画家がこちら側にいて、絵画が蝶番になっていて、その向こう側に「藤田」、言い換えれば藤田の絵画の総体が作る概念世界がある、というわけだ。だから、藤田の居ないチューリヒではあるけれども、確かにここに居た、という事実がより重みを持ってくるのだ。
藤田のリアリティに近づくには藤田が最も長い時間を過ごしたパリに行かねばならないだろう。パリ、特にモンパルナスには藤田の残像が藤田の歩いた道や訪ねた場所に残されているのではないか。そこを歩くことでこちら側の藤田を私の想像力の中に甦らすことができるかもしれない。
藤田終焉の地チューリヒから時間をさかのぼり藤田が生きていたパリを歩くこととしよう。藤田嗣治の歩いたパリを私も歩くのだ。