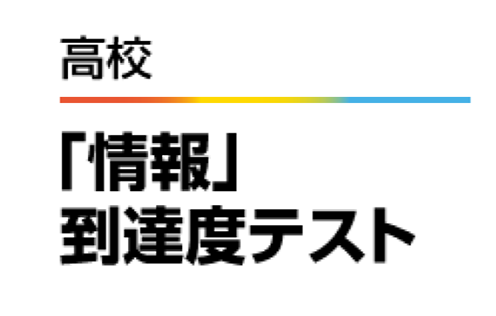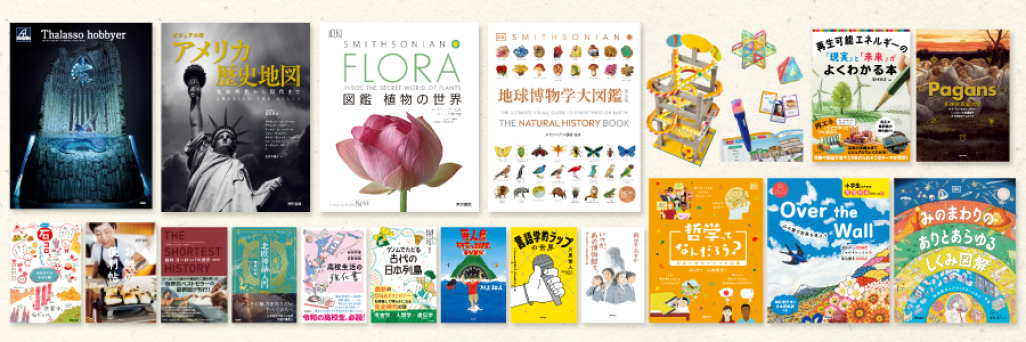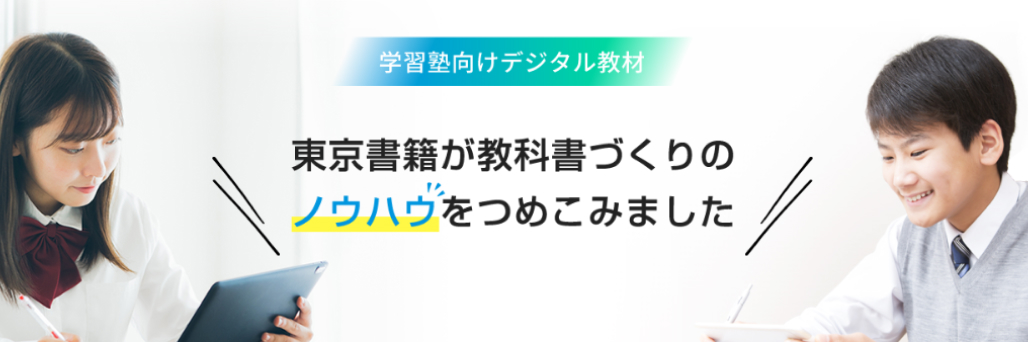ディスレクシア 読み書きのLD 親と専門家のためのガイド
マーガレット・J・スノウリング/著 加藤醇子,宇野 彰/監訳 紅葉誠一/訳
ISBN:978-4-487-79725-7
定価4,620円(本体4,200円+税10%)
発売年月日:2008年02月01日
ページ数:368頁
判型:A5
解説:
学習障害の中核といわれる読み書きの障害ディスレクシアの確かな教科書。これまで英語圏中心で行われてきた研究がまとめられ今後進むべき方向が示されている,欠くべからざる関係者必携の基本図書。
学習障害の中核といわれる読み書きの障害ディスレクシアの確かな教科書。これまで英語圏中心で行われてきた研究がまとめられ今後進むべき方向が示されている,欠くべからざる関係者必携の基本図書。
コンテンツ
図表一覧
謝辞
まえがき
日本語版に寄せて
第1章 ディスレクシアとは
JMの症歴
読み、綴り、音韻スキルの発達
代償的方略の発達
ディスレクシアにおける綴りの発達
第2章 ディスレクシアの定義
ディスレクシアの医学モデル
特異的読み障害
全般的知的遅れによる読みの困難な児童と特異的読字障害のある児童との違い
ディスクレパンシーによるディスレクシアの定義は正しいか
ディスレクシアの発達モデル
第3章 音韻表象仮説
比較対照群の問題
読み年齢対応法
言語性の障害としてのディスレクシア
ディスレクシアにおける音韻的障害
音声言語の短期記憶の障害/呼称の障害/ラピッドネーミング/復唱/語音認知/
ディスレクシア児における語音の同定/ディスレクシアにおけるメタ音韻障害/音韻学習
音韻表象レベルの中核的障害としてのディスレクシア
第4章 読みと綴りの学習
読みの学習
読みの発達段階モデル/異なる発達のパターン/アルファベットの原則の獲得/
音韻スキルの役割――音素と韻のどちらが基礎になっているか
単語の認識力の発達――個別認識モデル
綴りの学習
読みと綴りの学習に関する長期的研究
音韻能力の構造
文字の知識が担っている役割
読み学習のコネクショニストモデル
サイデンバーグとマクレランドのモデル
読み学習における「意味」の役割
第5章 ディスレクシア――書き言葉の障害
ディスレクシア児が読みを苦手とする理由
ディスレクシア児の非語の音読スキル
単語の綴りの規則性がディスレクシアに与える影響
ディスレクシア児における綴り
話し言葉と綴りに関する継続的問題
綴りにおける特異的な問題
第6章 ディスレクシアの個人差
ディスレクシア児の分類
ディスレクシアの読みと綴りの特性
発達性読み障害と後天性読み障害の関連性
症例群からのアプローチ
回帰を用いた下位分類の試み
ディスレクシア児の非語と不規則語の読み能力を予測する指標
第7章 音韻障害の重さの程度による仮説
音韻的発達の質的な差異
「重さの程度」仮説による症例検討
音韻障害のある児童の読みと綴りの学習
音韻出力と綴りの発達
ディスレクシアを一元的に定義することは可能か
第8章 ディスレクシアの生物学的基盤
ディスレクシアの遺伝性
読みの下位スキルの遺伝性
ディスレクシアにおける個人差の遺伝性
ディスレクシアの遺伝的基盤
就学前児童の前駆症状
ディスレクシアと脳
側性化と免疫疾患とディスレクシアの関係
第9章 ディスレクシアは感覚障害か
視覚処理障害としてのディスレクシア
「一時的」な視覚系の障害
ディスレクシアの人と読み健常者の動きの識別
ディスレクシアにおける時間的処理の障害
ディスレクシアにおける聴覚処理障害
全感覚障害についての根拠
第10章 ディスレクシア克服のための支援
良い指導法についての研究
読み困難の予防
読み困難のリスクのある児童への早期介入
読み学習への介入
介入に対する子どもの反応の個人差
般化に関する留意点
第11章 習熟と不完全さ――補償的教育の役割
音韻障害がある子どもに読み書きを習得させるには
言語スキルと読みの学習
読みの学習における音韻スキルと意味スキルの相互作用
環境要因の役割
異なる言語間の要因/読みの練習
重複症状の問題
ディスレクシアの定義に向けて
第12章 まとめならびに今後の見通し
付録 発達性ディスレクシアの英語と日本語の言語間研究
日本語における読み書き障害と文字列から音韻列変換時の粒の大きさと透明性の仮説
タエコ・ナカヤマ・ワイデル
Taeko Nakayama Wydell, Ph.D.
日本語の書記体系(表記)
日本語のかな/日本語の漢字
日本のディスレクシア
「粒性と透明性の仮説」
AS:英語・日本語バイリンガルで一言語のみにディスレクシアが見られる症例
ASの日本語の読み
漢字/仮名
ASの英語での検査成績
(1) ASと英語ネイティブの対照群
(2) ASと日本人および英語ネイティブ被験者の対照群との比較
考察
一般的考察
本項参考文献
監訳者あとがき………………加藤醇子
監訳者あとがき………………宇野 彰
参考文献
人名・団体索引
事項索引
支援・研究団体
著者・監訳者・訳者紹介
謝辞
まえがき
日本語版に寄せて
第1章 ディスレクシアとは
JMの症歴
読み、綴り、音韻スキルの発達
代償的方略の発達
ディスレクシアにおける綴りの発達
第2章 ディスレクシアの定義
ディスレクシアの医学モデル
特異的読み障害
全般的知的遅れによる読みの困難な児童と特異的読字障害のある児童との違い
ディスクレパンシーによるディスレクシアの定義は正しいか
ディスレクシアの発達モデル
第3章 音韻表象仮説
比較対照群の問題
読み年齢対応法
言語性の障害としてのディスレクシア
ディスレクシアにおける音韻的障害
音声言語の短期記憶の障害/呼称の障害/ラピッドネーミング/復唱/語音認知/
ディスレクシア児における語音の同定/ディスレクシアにおけるメタ音韻障害/音韻学習
音韻表象レベルの中核的障害としてのディスレクシア
第4章 読みと綴りの学習
読みの学習
読みの発達段階モデル/異なる発達のパターン/アルファベットの原則の獲得/
音韻スキルの役割――音素と韻のどちらが基礎になっているか
単語の認識力の発達――個別認識モデル
綴りの学習
読みと綴りの学習に関する長期的研究
音韻能力の構造
文字の知識が担っている役割
読み学習のコネクショニストモデル
サイデンバーグとマクレランドのモデル
読み学習における「意味」の役割
第5章 ディスレクシア――書き言葉の障害
ディスレクシア児が読みを苦手とする理由
ディスレクシア児の非語の音読スキル
単語の綴りの規則性がディスレクシアに与える影響
ディスレクシア児における綴り
話し言葉と綴りに関する継続的問題
綴りにおける特異的な問題
第6章 ディスレクシアの個人差
ディスレクシア児の分類
ディスレクシアの読みと綴りの特性
発達性読み障害と後天性読み障害の関連性
症例群からのアプローチ
回帰を用いた下位分類の試み
ディスレクシア児の非語と不規則語の読み能力を予測する指標
第7章 音韻障害の重さの程度による仮説
音韻的発達の質的な差異
「重さの程度」仮説による症例検討
音韻障害のある児童の読みと綴りの学習
音韻出力と綴りの発達
ディスレクシアを一元的に定義することは可能か
第8章 ディスレクシアの生物学的基盤
ディスレクシアの遺伝性
読みの下位スキルの遺伝性
ディスレクシアにおける個人差の遺伝性
ディスレクシアの遺伝的基盤
就学前児童の前駆症状
ディスレクシアと脳
側性化と免疫疾患とディスレクシアの関係
第9章 ディスレクシアは感覚障害か
視覚処理障害としてのディスレクシア
「一時的」な視覚系の障害
ディスレクシアの人と読み健常者の動きの識別
ディスレクシアにおける時間的処理の障害
ディスレクシアにおける聴覚処理障害
全感覚障害についての根拠
第10章 ディスレクシア克服のための支援
良い指導法についての研究
読み困難の予防
読み困難のリスクのある児童への早期介入
読み学習への介入
介入に対する子どもの反応の個人差
般化に関する留意点
第11章 習熟と不完全さ――補償的教育の役割
音韻障害がある子どもに読み書きを習得させるには
言語スキルと読みの学習
読みの学習における音韻スキルと意味スキルの相互作用
環境要因の役割
異なる言語間の要因/読みの練習
重複症状の問題
ディスレクシアの定義に向けて
第12章 まとめならびに今後の見通し
付録 発達性ディスレクシアの英語と日本語の言語間研究
日本語における読み書き障害と文字列から音韻列変換時の粒の大きさと透明性の仮説
タエコ・ナカヤマ・ワイデル
Taeko Nakayama Wydell, Ph.D.
日本語の書記体系(表記)
日本語のかな/日本語の漢字
日本のディスレクシア
「粒性と透明性の仮説」
AS:英語・日本語バイリンガルで一言語のみにディスレクシアが見られる症例
ASの日本語の読み
漢字/仮名
ASの英語での検査成績
(1) ASと英語ネイティブの対照群
(2) ASと日本人および英語ネイティブ被験者の対照群との比較
考察
一般的考察
本項参考文献
監訳者あとがき………………加藤醇子
監訳者あとがき………………宇野 彰
参考文献
人名・団体索引
事項索引
支援・研究団体
著者・監訳者・訳者紹介