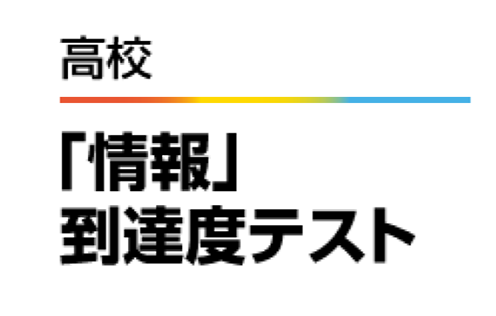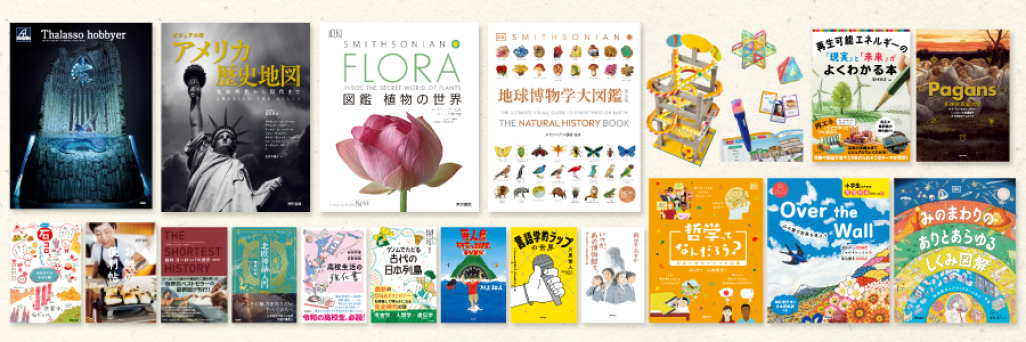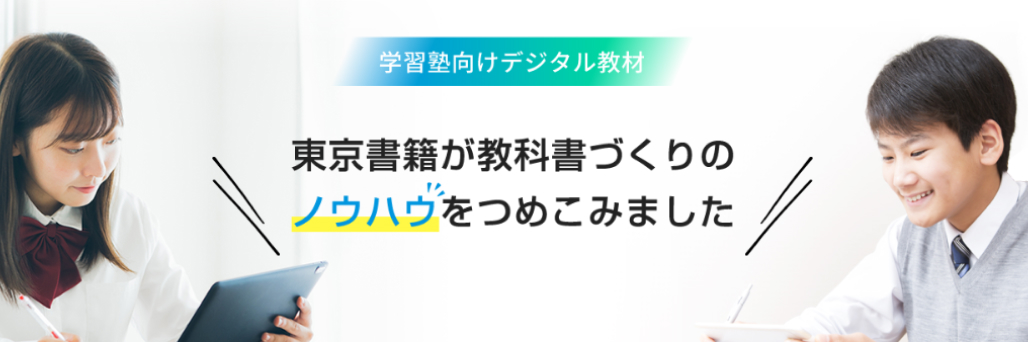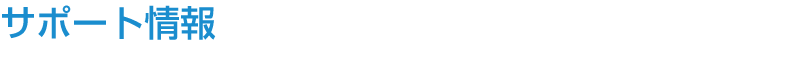中学校 EduTown SDGs 2年
茨城県茨城大学教育学部附属中学校
■茨城大学教育学部附属中学校 先生インタビュー2(2024年3月19日)
Q 今日の授業を見ていかがでしたか?
今日の奥谷先生の授業のグローバル市民科は、問題発見解決学習です。問題・課題を見つけることから学習が始まります。だから、先生の手の平の上で動いている学習ではなく、いろんなフィールドワークをしたり、いろんな人に話を聞いたりして、生徒たちが「もっとこれは解決していかなくちゃいけない」とか「ここに課題がある」と見つけて学習を進めます。課題意識を自分のものにして、解決していく。それこそが探究学習だと思っています。
Q 問題・課題をみんな見つけられますか?
深い問題・課題が見つけられる生徒もいれば、深くない問題・課題しか見つけられない生徒もいる、それが重要だと思うんですね。今までの一斉学習では、100点満点のテストで前回20点だった生徒が30点をとって、先生が「10点上がったね」と言っても、生徒からすると100点が満点だから「いや、30点じゃ…」となるじゃないですか。
問題発見解決学習のいいところは、自分に合ったルーブリックを作っていけるということなんですね。私は、深い課題を全員が見つけられなくていいと思っています。これまでの学習で良くないところは、勉強があっという間に理解できて終わってしまう生徒、さらに発展していろいろなことをやりたい生徒、そういう生徒たちに「ここまでやったら、ちょっと待ってなさい」と頭を抑えて待たせることがありました。それだと思います。そういう生徒のルーブリックはもっと上の方にあるんですね。だから、どんどんもっと深く追求していく。
それに対して、それほど深くない課題に取り組んでいるように見える生徒でも、取り組んでいる課題はその生徒にとっては非常に深い課題だと考えて学習に取り組んでいます。だから、先生は「浅い」とか言ってはだめなんです。その生徒にとってみれば、その生徒なりに見つけた良い課題なのかも知れない。みんなが「そんなのわかってるよ」って言うかもしれない課題でも、その生徒が自分で見つけたとしたら、それは素晴らしいことです。先生は「あら、いいところに目をつけてがんばってるね」と言えばいい。課題は決して深くはないかもしれないが、その生徒にとってのルーブリックはそこがゴールなんだから、そこに向かって一生懸命やれたら最高だと思います。「そんなつまらない課題やって…」と言ったらだめなんです。もし、そういうことを言う先生がいるとすれば、「一つの課題、目標」という物差しで測っているわけで、一斉学習と同じになってしまいます。
附属中学校には、大学教員に負けないくらい「津波のハザードマップ」を研究している生徒がいたり、健康維持を図るためのソフトウェアを作成している生徒がいたりします。そういうふうに、人それぞれさまざまな興味に応じた研究を進めているのが「グローバル市民科」の素晴らしいところだと思います。
Q SDGsスタートブックについて
SDGsスタートブックは、すごくよくできていると思いますが、これだけで学習してはだめだと思うんですね。「今日はSDGsスタートブックの◯ページの勉強するよ」とやったら一斉学習になってしまいます。SDGsスタートブックを参考にして、自分が疑問や興味を持った課題を見つけるものにしてもらいたいなと考えています。
SDGsの学習は、先生方が教える時間ではないはずです。SDGsの17ある目標を全部覚える必要もありません。このSDGsスタートブックを読んで覚えても、5年後には課題が変わっていくと思います。そうではなく、これから大人になって、社会の中心になって生きていく生徒たちが、持続可能な社会をいかに自分で考えて、良い社会を作っていくか。グローバルだけじゃなくて、地域、会社、家庭だったりするかもしれないけれど、どう良い社会を実現していくか、が重要なのだと思います。17の目標を1個ずつやって17時間で終わります、という、そういう学習ではないわけです。それぞれの生徒が課題を見つけ、中間発表や成果発表で、お互いの意見を聞き合ったりして、「あ、そういうふうに考えてたんだね」とコラボレーションが始まったり、内容を修正したり、そういう学習になればいいと思います。
Q 先生方が授業観を変えていく必要があるのでしょうか?
探究学習は「グローバル市民科」だけではなく、教科の学習もそうなっていくべきだと思います。奥谷先生の授業は、ゴールがひとつじゃないオープンエンドな課題を提示して学習することが多いのです。そういう学習ってワクワクするし、生徒も主体的に活動しています。
もちろん覚えなくてはいけないこともあるでしょうけども、やはり生徒が学びたいという気持ちがなければ、いくら教師サイドがインプットしようと思っても入らないわけですから。それを一方的に先生が説明したって、それは教師の自己満足で終わってしまうので、それじゃいけないなと思います。
私は100点を取ることだけが重要ではないと思っています。100点取れない生徒もいっぱいいます。でも、100点を取らないと大学に入れないとか、就職できない、そういうことはないわけです。だから、自分の興味関心のあることを伸ばしていく。 英語が好き、理科が好き、社会が好き、国語が大好き、体育が大好きとか、そういう自分の価値があるなと思うところを伸ばしてあげて、その内容が100点になったり、もしかしたら200点、300点になるといいなと思います。
先生から、決まり切った固定概念を聞くだけでは、つまらないですよね。そうではなくて、自分から学習に飛び込んでいって課題を見つけていけば、大きな成果があると思います。もしかしたら、失敗することもあるかもしれないけれど、その先に大成功が待ち構えている。そういうやっぱりワクワクするような 学習にしていかないといけないと考えています。 先生も探究学習ってよくわからないし、「困った困った」と言うかもしれないけど、やってみて途中で生徒が挫折しても、「何がダメだったのかな」って、それを見つけるだけでもすごく良い学習だと思います。
そもそも先生も、生徒と一緒になってワクワク楽しい探究学習にしなきゃだめだと思います。先生方がワクワクしないと生徒たちもワクワクしないですよ。今日の奥谷先生も、生徒と一緒になって本当に楽しんでいました。日々、本校の先生方は、生徒と一緒に楽しんで授業してます。先生も知らないことをやって、「わあ、そんなことわかったの」と声があがるような学習になっていくと、本物の学習になるのではないかと思います。そのような授業を見ていて、この生徒たちの将来が楽しみだなと思います。
そういうきっかけとして、このSDGsスタートブックを活用してもらって、こういう世界がある、こういう課題がある、じゃあもっと深く調べてみようと、そういうヒントになるといいなと思います。ぜひ、ワクワクする授業の入り口として活用してはいかがでしょうか。
※執筆者の所属や役職は執筆時のものです