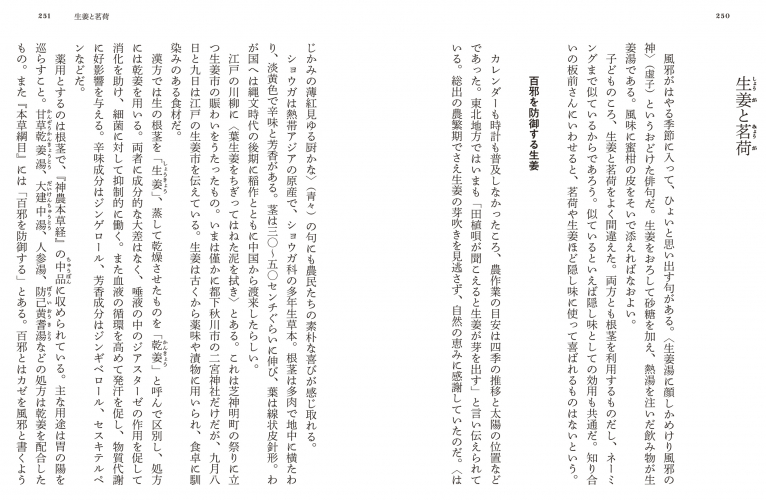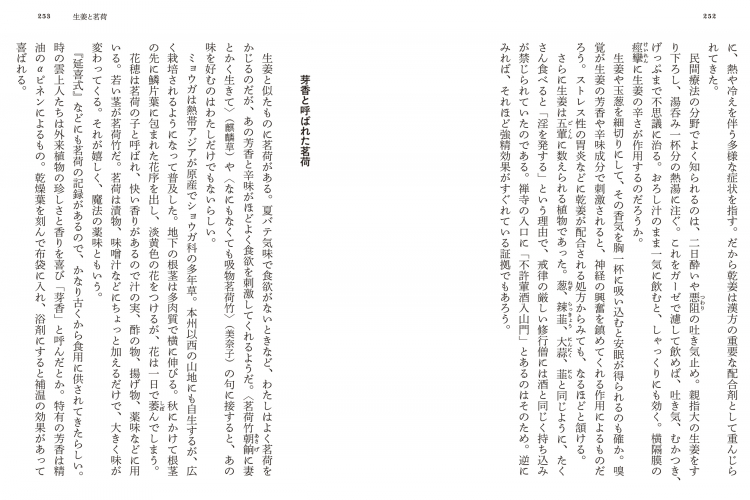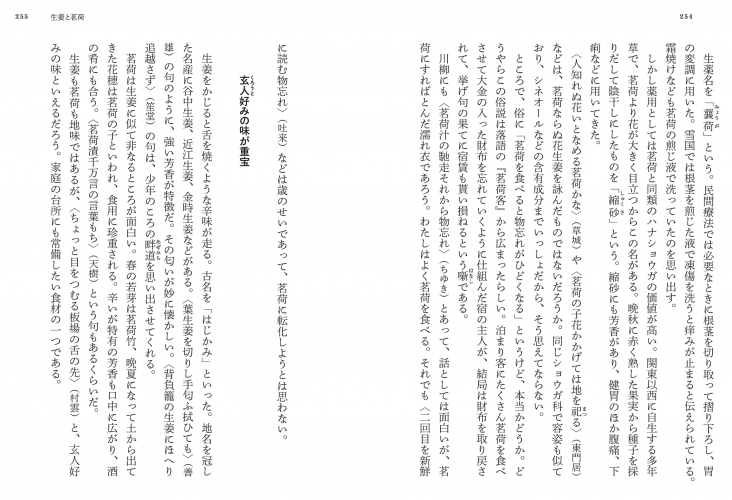身近な「くすり」歳時記
ISBN:978-4-487-81330-8
定価1,760円(本体1,600円+税10%)
発売年月日:2019年12月21日
ページ数:376頁
判型:四六判
暮らしの中にある身近な「くすり」。
先人たちから受け継いだ、生活の知恵。
古来使われてきた身近な「くすり」である生薬・漢方薬を、12カ月の月別にあげ、行事や気候、文化・風習とともに歳時記として語る。
一月 屠蘇と七草 松竹梅 白朮と南天 蜜柑と落花生
二月 梅と蓬 土筆と蕗 椿と水仙 片栗と繁縷
三月 土と水 桃と連翹 大葉子と錨草 辛夷と木瓜
四月 桜と月桂樹 甘茶と山葵 甘草と独活 梔子と山椒
五月 笹と菖蒲 人参と熊胆 藤と紫陽花 牡丹と芍薬
六月 紫蘇と薄荷 十薬と玉葱 枇杷と杏 牛乳とチーズ
七月 麦茶と麦酒 大蒜と辣韮 桜桃と紅花 胡瓜と茄子
八月 朝顔と枸杞 鳩麦と玉蜀黍 黄柏と蒲 胡麻と鬱金
九月 生姜と茗荷 竜胆と千振 茜と玄草 糸瓜と胡桃
十月 茸と葛 山芋と納豆 柿と林檎 葡萄と通草
十一月 菊と銀杏 花梨とアロエ 葱と大根 サフランと木蓼
十二月 柚子と南瓜 河豚と鮟鱇 膃肭臍と鼈 酒
はじめに
わたしたちの先人は、若芽が萌えるのを待ちかねて、いそいそと野山に出かけた。若草や木の芽を摘んで食べ、自然の精気を体内に採り入れようと試みたのである。草の根や木の実が成熟する秋になると、人々はまた勇んで野山をめざした。大地の養分と太陽の光を濃縮したような根や実には、すぐれた薬効を示すものが多い。
春の摘み草のことを「薬摘み」といい、秋は「薬掘り」という。それは自然の恵みを得ようとする風習であり、生活の知恵の伝承の場でもあった。わたしたちの祖先は、自然に生育した草や木の実、ふくらんだ根、小動物の卵や虫などを食べていたと想像される。時には中毒を起こして苦しみも体験し、口づてに注意を促してきたことだろう。
やがて悪いものを食べたときには嘔吐をさせる草とか、下痢をさせる根などを使い分けながら体調を整える方法を考えた。そして食料としての草木とは別に、健康を維持するのに必要な天然資源をたくさん発見してきたのである。それが「生薬」(しょうやく)であり、組み合わせて製剤化したものを「漢方薬」と呼ぶようになったのだ。
1400年も前に書かれた中国の古典『神農本草経』(しんのうほんぞうきょう)には、すでに365種類の生薬が収められている。400年前の『本草綱目』(ほんぞうこうもく)では1890にも膨らんだ。そしていまも漢方の世界では、これらの古典を叩き台にしながら天然資源を薬用にする試みが地道に繰り返されている。
漢方という呼び名は日本独自のものだ。江戸時代に伝来した蘭方と区別するためにこう 呼ばれたもので、中国の漢代に発達した医療技術を源流とする学問という意味であろうか。漢方薬を用いる治療法だけでなく、あんま、鍼灸などの物理療法や養生法も含んでいる。い わば中国で生まれ、日本で育った医療技術が漢方といえるだろう。
そして漢方では、生薬を3つに分けて考えた。体を丈夫にして長期に投与しても害がないものを上品(じょうぼん)、毒性は弱いが作用はやや強いものを中品(ちゅうぼん)、激しい作用があって長く用いるべきでないものを下品(げぼん)という。これらの生薬をうまく組み合わせて、できるだけ副作用のない処方を工夫してきたのである。
わたしが興味深く思うのは、単味の生薬としては成分がわかっていなくても、経験的に効能の知られた生薬を処方に組み込むと、現代医学では治りにくい慢性疾患にも期待にたがわぬ治癒力を発揮することだ。そして構成生薬の1つをはぶいただけでも極端に効力を失う不思議さ。3000年の実績で構築された漢方の妙味である。
もちろん漢方は、全人的に診て投薬するものなので、体質に合わなければ効かない。そのために漢方には、望、聞、問、切の独得な診断法があり、その基準として陰陽、虚実、表裏、寒熱の判断がある。同じ疾患だからといって同じ薬を使うとは限らない。靴に足を合わせる現代薬の使い方とは基本的に違うのだ。
だから漢方的にみると、安易にのんでいる現代薬の多くは下品ということになる。即効性はあるが副作用を伴うからだ。ところが実際にはどうか。ちょっと子どもが風邪気味といっては医者に飛んで行き、甘いシロップ剤をのませ続ける。抗生物質であろうと頓着しない。薬害の原因を自らつくっていることに気づかないのだ。恐るべき風潮ではないだろうか。
わたしが子どものころは、風邪を引いてもすぐ薬を与えるような親はいなかった。生姜湯(しょうがとう)を飲まされ、葛湯(くずゆ)や金柑(きんかん)の砂糖漬けを食べさせられて、おとなしく寝ていなさい、といわれたもの。林檎をすってもらって母親に甘えられるスキンシップも嬉しかった。それだけで数日も経てば治ってしまったように記憶している。
いま、生活が豊かになって洟垂(はなた)れ小僧もいなくなったし、トラコーマや寄生虫のような疾患は少なくなったが、半面では安易な薬の使い過ぎから病菌の抵抗力が強くなり、花粉症やアトピーなどの新たなアレルギー疾患は増えてきた。養生もしないまま薬をのむ習慣を断ち切らない限り、この悪循環は消えないだろう。生きざままでインスタント文明に毒されてしまったような気がしてならない。
こんな時代だからこそ、わたしは新しい薬の概念が必要なのだと思う。自然の恵みを経験的に受け継いできた知恵を、暮らしの基礎に据えるべきだと痛切に感じている。そんな思いから食べ物や民間療法まで含めた身近な薬を書き出してみた。
いわば暮らしの中にある身近な平仮名の「くすり」であり、医食同源につながる薬のルーツである。核家族化が進むにつれて若い世代が失ってしまった生活の知恵を伝達することが、この本の願いにほかならない。